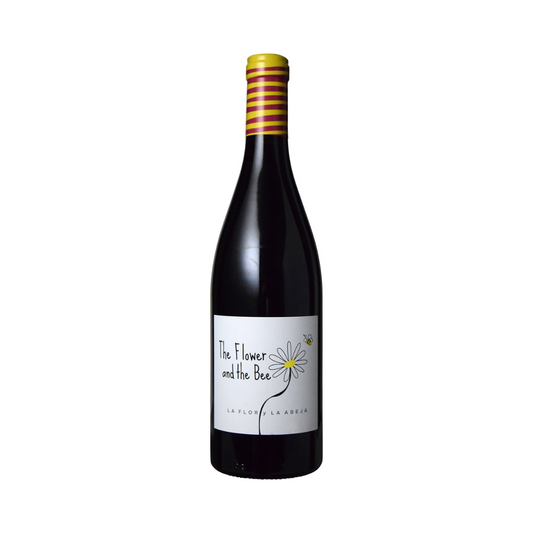こんにちは、CalivinoのManamiです。
今日は「ワイン テイスティング」をテーマに、初心者の方から少し経験のある方まで楽しめるような内容をまとめてみました。私自身、初めてワイン会に参加したとき、周りの人が次々と「このワインはブラックチェリーの香りがしますね」とか「スパイスのニュアンスがあります」と言っているのを聞いて、正直「え?本当にそんな風にわかるの?」と驚いたことがあります。ワインは好きだったけれど、当時はまだ「赤は渋い、白はすっきり」くらいの感覚しかなくて、テイスティングという言葉の意味さえよくわかっていませんでした。
でも、学んでいくうちに「ワインテイスティングは特別な人だけができるものではなく、誰でも段階を踏めば楽しめるもの」だと気づきました。今回はその経験も交えながら、ワインテイスティングの基礎から実践方法、家で楽しむコツ、そしてワイン会でのスマートな振る舞いまでを解説していきます。
ワインテイスティングとは?目的と魅力
まず、「ワインテイスティングってそもそも何をすること?」という疑問から。テイスティングとは、単にワインを飲むことではなく、色・香り・味わいを意識的に感じ取り、言葉で表現することを指します。
ワインテイスティングの目的
-
ワインの品質やスタイルを知る
-
自分の好みを発見する
-
食事やシーンに合うワインを選べるようになる
特に初心者にとって大切なのは、「自分がどんなワインを好きなのか」を知ることです。赤ワイン一つ取っても、ライトボディのピノ・ノワールとフルボディのカベルネ・ソーヴィニヨンでは、全く印象が違います。その違いを楽しみながら少しずつ表現できるようになると、ワインライフはぐんと豊かになります。
ワインテイスティングの5ステップ
テイスティングは難しそうに感じるかもしれませんが、実は大きく分けて5つのステップに整理できます。
1. 見る(外観)
グラスを白い背景にかざして、色合いや透明感を観察します。
-
若い赤ワイン → 紫がかったルビー色
-
熟成した赤ワイン → レンガ色やオレンジがかった色調
-
白ワイン → レモンイエローから黄金色へ変化
ワインの年齢やブドウ品種によって外観は大きく変わるので、視覚から得られる情報は意外と多いのです。
2. 回す(スワリング)
グラスを軽く回すことで、ワインの香り成分が空気と触れて広がります。最初はこぼしそうでドキドキしますが、テーブルにグラスを置いたまま小さく回せば安心です。
3. 香る(アロマ)
鼻を近づけて香りを感じます。最初は「アルコールっぽい」としか思えなくても大丈夫。少しずつ「果物の香り?」「花のようなニュアンス?」と、ざっくりで構いません。
-
赤ワイン → ブラックベリー、チェリー、スパイス
-
白ワイン → レモン、リンゴ、花、ハチミツ
-
熟成ワイン → キノコ、レザー、トリュフ
4. 味わう(口中)
一口含んで、舌の上で広がる感覚を意識します。
-
酸味:舌の横に感じる爽やかさ
-
甘み:舌の先に残るまろやかさ
-
渋み(タンニン):舌や歯茎の乾いた感覚
-
アルコール感:喉の温かさ
-
余韻:飲み込んだ後にどれくらい香りが続くか
5. 表現する
最後に感じたことを言葉にしてみましょう。最初は「すっきり」「濃厚」くらいで十分です。少しずつ「ベリーの香り」「バニラのニュアンス」などと表現の幅を広げると、楽しみが倍増します。
香りの表現を磨くコツ
私も最初は「どうやったらそんなに香りを言い当てられるの?」と不思議でした。でもコツはシンプルで、日常の香りに意識を向けることなんです。
-
朝のフルーツを食べるときに「これは柑橘系の爽やかさ」
-
コーヒーを淹れたときに「ローストの香ばしさ」
-
花屋の前を通るときに「フローラルな香り」
こうした経験を積み重ねることで、ワインを飲んだときに「あ、これはあの香りに似てる」と気づけるようになります。
家でできるワインテイスティングの楽しみ方
ソムリエの資格がなくても、家庭で十分テイスティングは楽しめます。
おすすめの準備
-
グラス:チューリップ型のワイングラスが香りをとらえやすい
-
温度:赤は16〜18℃、白は8〜12℃が目安
-
ノート:感じたことをメモしておくと後で比較できる
練習の仕方
-
同じブドウ品種で産地違いを飲み比べる
-
例:ピノ・ノワール(フランス・ブルゴーニュ vs アメリカ・オレゴン)
-
-
同じ産地で品種違いを飲み比べる
-
例:ボルドーのメルロー vs カベルネ・ソーヴィニヨン
-
こうすることで違いがはっきりわかり、テイスティングの理解が深まります。
ワイン会やレストランでのスマートな振る舞い
「周りの人みたいに上手に表現できないから恥ずかしい」という気持ち、私もよくわかります。でも大切なのは感じたことを素直に言うこと。難しい表現は必要ありません。「フルーティで飲みやすい」「少し渋いけど食事に合いそう」など、シンプルで十分です。
レストランでのテイスティングも同じ。ソムリエが注いでくれるときは、香りと味を軽く確かめ、「問題ありません」と伝えればOKです。変に格好をつける必要は全くありません。
まとめ|ワインテイスティングを日常に取り入れてみよう
今日は「ワイン テイスティング」の基本について、初心者にもわかりやすく解説しました。
-
テイスティングは特別な人だけのものではなく、誰でもできる
-
5つのステップ(見る・回す・香る・味わう・表現する)が基本
-
香りや味わいを表現するには、日常の体験を活かす
-
家でも手軽に練習できる
-
レストランやワイン会ではシンプルに楽しめばOK
ワインは飲むだけでももちろん楽しいですが、テイスティングを通して一歩踏み込むと、奥深さがぐんと広がります。ぜひ次のワイン会や家飲みで、今日の内容を実践してみてください。新しい発見がきっとありますよ。乾杯!