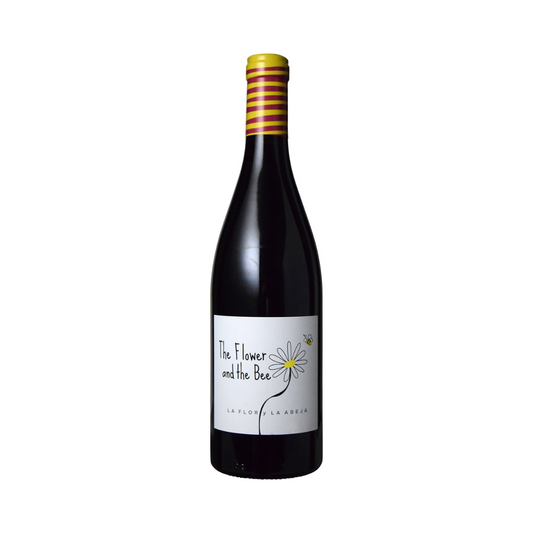こんにちは、CalivinoのManamiです。
あなたは「リンゴのお酒」と聞いて、何を思い浮かべますか?
おそらく、多くの方が「シードル(Cidre)」を想像するのではないでしょうか。
私もそうでした。
特にここ数年、クラフトシードルがブームになり、カフェでガレットと合わせたり、ビールの代わりにゴクゴク飲める辛口シードルを楽しんだりと、その魅力にはすっかりハマっていました。
「リンゴのお酒=シードル」。私の中では、すっかりその図式が出来上がっていたんです。
その固定観念が覆されたのは、昨年の秋、旅行で訪れた長野県でのことでした。
リンゴの名産地だけあって、お土産屋さんやワイナリーにはシードルがたくさん並んでいます。
「どれにしようかな」と見ていると、棚の隅に、シードルとは明らかに違う雰囲気のボトルを見つけたのです。
それは、シードルのような発泡性の王冠(栓)ではなく、ワインと全く同じ「コルク」で栓がされた、750mlのボトル。
ラベルには、フランス語の「Cidre」ではなく、はっきりと英語で「Apple Wine(アップルワイン)」と書かれていました。
「アップルワイン…? シードルと、何が違うんですか?」
お店の方に尋ねると、にっこり笑ってこう教えてくれました。
「ああ、それはね、**シードルが『リンゴのスパークリング』なら、アップルワインは『リンゴのスティルワイン』**なんですよ。アルコール度数も、ほら」
ラベルを見ると、アルコール度数は「11%」。
シードルが大体2%~8%くらいなのに対し、これはもう、白ワインと全く同じです。
興味津々で購入し、その夜、ホテルの部屋でワイングラスに注いで、私は二度目の衝撃を受けました。
泡は、ない。
香りは、リンゴジュースのような単純な甘さではなく、熟したリンゴや蜜、そしてほんのり酵母の複雑な香り。
一口飲むと…
「……辛口! そして、酸がキレイ!」
シードルのような爽快感とは違う、しっかりとした骨格と、白ワインに引けを取らないシャープな酸味。そして、飲みごたえのあるアルコール感。
「これ、シードルじゃない。紛れもなく『ワイン』だ…!」
それは、私が知っていた「リンゴのお酒」の概念を、根本からひっくり返す出会いでした。
この記事では、そんな「アップルワイン」の魅力について、ワイン好きの視点から、シードルとの決定的な違い、その味わい、そして楽しみ方まで、徹底的に深掘りしていきます。
ワインは好きだけど、アップルワインは未体験。
シードルとの違いがよくわからない。
そんなあなたにこそ、読んでほしい。
ブドウだけがワインじゃない。リンゴが持つ「ワイン」としてのポテンシャルに、あなたもきっと驚くはずです。
決定的な違いはココ!「アップルワイン」と「シードル」を徹底比較
まず、一番の疑問から解き明かしましょう。「アップルワイン」と「シードル」、この二つは具体的に何がどう違うのでしょうか。
どちらも「リンゴ果汁を発酵させた醸造酒」であることは同じ。ですが、その「目指すゴール」が全く違うのです。
シードル(Cidre / Cider)とは?
まずは、お馴染みのシードルから。
シードルは、フランス(ブルターニュ地方やノルマンディー地方)やイギリスが本場で、その最大の特徴は「発泡性(スパークリング)」であることです。
-
アルコール度数: 低め(2% 〜 8%程度)
-
泡の有無: あり(発泡性)
-
味わい: 甘口(Doux)から辛口(Brut)まで多様。
-
飲み方: 冷やして、ゴクゴクと爽快に楽しむ。ビールやスパークリングワインに近い立ち位置。
-
Manami的イメージ: 「リンゴのスパークリング酒」「リンゴのビール」
アップルワイン(Apple Wine)とは?
一方、アップルワインは、シードルの「爽快感」とは別の方向性を目指します。
それは、ブドウで造る**「スティルワイン(非発泡性ワイン)」**に、どれだけ近づけるか、という挑戦です。
-
アルコール度数: 高め(10% 〜 13%程度)
-
泡の有無: なし(非発泡性=スティル)
-
味わい: 辛口(Dry)が主流。時に樽熟成させることも。
-
飲み方: 冷やして、ワイングラスで香りと味わいをじっくり楽しむ。
-
Manami的イメージ: 「リンゴの白ワイン」
なぜアルコール度数がこんなに違うの?
この「アルコール度数の差」こそが、二つを分ける決定的な鍵です。
お酒のアルコールは、果汁に含まれる「糖分」を酵母が分解することで生まれます。
リンゴ果汁に含まれる糖分を「全て」アルコールに変えると、大体6%〜8%程度のアルコール度数になります。
シードルの場合、
-
甘口(Doux): 発酵を「わざと途中で止めて」、糖分を残します。だから甘くてアルコールが低い(2%〜4%)のです。
-
辛口(Brut): 糖分を最後まで発酵させます。だから甘さがなくなり、アルコールは高め(6%〜8%)になります。
では、アップルワインの「11%」という度数はどこから来るのでしょう?
リンゴ果汁だけでは、ここまでのアルコールは生み出せません。
答えは、ワイン醸造でも使われる技術、「補糖(ほとう)」にあります。
「補糖(シャプタリザシオン)」とは、発酵前に果汁に「砂糖」を加え、アルコールの「素(もと)」となる糖分を人為的に増やしてあげる技術です。
これにより、酵母がより多くのアルコールを生み出せるようになり、ワイン(この場合はアップルワイン)のアルコール度数を10%以上に引き上げ、しっかりとした「骨格」と「飲みごたえ」を与えることができるのです。
つまり、シードルが「リンゴ本来の糖分」で造られるのに対し、アップルワインは「補糖」というワインの技術を使って、よりアルコール度数が高く、保存性の高い「スティルワイン」のスタイルを目指して造られている、ということです。
(※もちろん、例外的に補糖するシードルや、補糖しないアップルワインも存在します)
Manami的解釈:「ビール」と「ワイン」の違いに近いかも
この違い、ワイン好きの私たちには、こう例えると分かりやすいかもしれません。
-
シードル = ビールやスパークリングワイン
→ 喉越し、爽快感、泡の心地よさを楽しむ。アルコールは低めで、カジュアルに楽しみたい時に。
-
アップルワイン = スティルワイン(白ワイン)
→ 香り、味わいの複雑さ、酸味の骨格、そして食事とのペアリングをじっくり楽しむ。ワイングラスで向き合いたい時に。
「リンゴのお酒」という大きな括りの中でも、楽しみ方が全く違う、似て非なる存在。
それが、シードルとアップルワインなんです。
アップルワインの味と香りは?ワイン愛好家が唸るその魅力
「理屈はわかったけど、結局どんな味なの?」
「リンゴジュースにアルコール足した感じでしょ?」
そう思っている方にこそ、この章を読んでいただきたいです。
私が長野で出会ったあのアップルワインの味わいは、白ワイン好きなら絶対に「刺さる」ものでした。
「リンゴジュース」を想像したら絶対に裏切られる!
まず、甘いリンゴジュースのイメージは、一度捨ててください。
私が飲んだ辛口のアップルワインは、むしろ「シャープな酸味を持つ白ワイン」そのものでした。
-
香り:
グラスに注いだ瞬間、まず感じるのは、フレッシュな青リンゴやカリンのような、非常にクリーンな果実香。でも、それだけじゃない。
グラスを回すと、奥から蜜のような甘いニュアンス、そして発酵由来のパン生地(酵母)や、ほんのりナッツのような香ばしさが立ち上ります。
これは、高品質なシャルドネ(ブルゴーニュの白ワイン)や、リースリング(ドイツの白ワイン)にも通じる、複雑なアロマです。
-
味わい:
口に含んだ瞬間に感じるのは、「甘み」ではなく、「キレのある酸味」です。
リンゴの主な酸味は「リンゴ酸(Malic Acid)」。これはブドウの「酒石酸(Tartaric Acid)」とはまた違う、シャープで爽快な酸味。
その酸が、11%のアルコール感としっかりとしたボディ(酒質)を下支えしている。
飲み込んだ後も、リンゴの香りが鼻に抜け、スッとキレていく。
-
結論:
「これは、食中酒だ」
そう直感しました。甘ったるさは皆無。むしろ、料理の脂をスッキリと洗い流してくれる、白ワインとしての完璧な資質を備えていました。
スタイルは多様!「甘口」や「樽熟成」も
もちろん、私が飲んだ「辛口スティル」だけがアップルワインではありません。
ブドウのワインと同じように、そのスタイルは多様です。
-
辛口(Dry)
今説明したような、食中酒としてのポテンシャルが最も高いタイプ。
-
中辛口(Semi-Dry / Off-Dry)
ほんのりとリンゴの甘みを残したタイプ。スパイシーな料理や、甘辛い味付けの料理と合わせるのに向いています。
-
甘口(Sweet)
デザートワインの立ち位置。特に、カナダのケベック州などで造られる「アイス・シードル(Ice Cider)」は、アップルワインの最高峰とも言われます。
これは、凍らせたリンゴや果汁から糖分を凝縮させて造る、まさにリンゴの「貴腐ワイン」や「アイスワイン」。アルコール度数は7%〜13%と幅広く、非発泡性のものが多いため、甘口アップルワインのカテゴリーに入ります。
-
樽熟成(Oak-Aged)
白ワインと同じように、発酵や熟成にオーク樽を使う生産者もいます。
樽由来のバニラやトースト、ココナッツのような香ばしさがリンゴの風味に加わり、シャルドネの「樽ドネ」のような、非常にリッチで複雑な味わいを生み出します。ワイン好きなら、ぜひ探してみたいスタイルですね。
なぜ造るのが難しい?「自家製アップルワイン」と法律の壁
アップルワインについて調べると、「自家製」「作り方」というキーワードがたくさん出てきます。
海外、特にアメリカやカナダでは、リンゴ農家が自家製アップルワインを造る文化が根付いており、家庭で楽しむ「ホームブルーイング」のキットなども人気です。
「じゃあ、日本でもリンゴジュースで造れるかも?」
そう思ったあなた、ここで大きな注意喚起が必要です。
日本では「酒税法」で厳しく制限されています
結論から言うと、日本国内で、アルコール度数1%以上のお酒を「無免許で」造ることは、酒税法で固く禁じられています。
-
酒税法 第七条(酒類の製造免許):
酒類を製造しようとする者は、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。
これに違反した場合、「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という非常に重い罰則が科されます。
「自分で飲むだけだから」という言い訳は一切通用しません。
「梅酒」はOKで、なぜ「アップルワイン」はNGなの?
「え、でも、家で梅酒や果実酒を造るのはOKじゃない?」
良い質問です。これも酒税法で明確にルールが決められています。
家庭で梅酒などを造ることが許されている(例外的に黙認されている)のは、以下の「2つの条件」を両方満たしている場合のみです。
-
「焼酎(ホワイトリカー)」など、アルコール度数20%以上の「すでに免許を受けて製造されたお酒」に漬け込むこと。
-
ブドウ(ヤマブドウ含む)や穀類(米、麦など)を「原料として使用しない」こと。
(※これらを原料に使うと、新たにワインやビール、どぶろくを「醸造」したとみなされるため)
つまり、「梅酒」は、アルコールをゼロから生み出す「醸造」ではなく、すでにあるお酒に風味を移す「混成」だから許されているのです。
一方、「アップルワイン」は、リンゴジュース(アルコール0%)に酵母を加え、アルコールを「ゼロから生み出す=醸造」する行為です。
これは、無免許で行えば完全に「密造酒」となり、法律違反になってしまいます。
合法的に楽しむ道は「海外」か「購入」のみ
自家製アップルワインに挑戦したい!というロマンはとてもよく分かりますが、日本に住む限り、合法的な道は以下の2択です。
-
海外で楽しむ:
ホームブルーイングが合法な国(アメリカの多くの州など)で、趣味として楽しむ。
-
プロが造ったものを「購入する」:
日本国内にも、長野や青森を中心に、素晴らしいアップルワインを造る免許を持った生産者さん(ワイナリーやサイダリー)がたくさんいます。
私たちがすべきことは、法律を犯すリスクを負うことではなく、彼らが情熱と技術を注ぎ込んで造った、美味しくて安全なアップルワインを「応援して買う」ことだと、私は思います。
アップルワインの選び方とおすすめ産地
では、私たちが「買う」べき素晴らしいアップルワインは、どこで出会えるのでしょうか?
ワインショップやネットで探す際のヒントをご紹介します。
まずは「国産」!二大産地「長野」と「青森」
やはり、日本のリンゴ二大産地は外せません。
シードル造りが盛んなこれらの地域では、近年、ワイン醸造の技術を応用した本格的な「アップルワイン」の生産にも力を入れています。
-
長野県:
ワイナリーが多い土地柄、ブドウと同じ醸造設備を使ってアップルワインを造る生産者が増えています。「ふじ」だけでなく、「紅玉(こうぎょく)」のシャープな酸味を活かしたり、「シナノゴールド」の芳醇な香りを引き出したりと、品種ごとの個性を楽しむことができます。
-
青森県:
日本一のリンゴ産地。こちらもシードルが有名ですが、スティルタイプのアップルワインも非常に高品質。リンゴを知り尽くした生産者が造る、バランスの取れた味わいが魅力です。
ワイン好きが注目する「カナダ」と「アメリカ」
海外に目を向けると、さらに多様なスタイルに出会えます。
-
カナダ(特にケベック州):
前述した「アイス・シードル(Ice Cider)」の聖地。
極寒の気候を活かした氷結搾り(クリオ・エクストラクション)で造られる、極甘口のデザート・アップルワインは、まさに「飲むアップルパイ」のような官能的な美味しさ。ワイン愛好家なら、一度は試してほしい逸品です。
-
アメリカ(ニューイングランド地方、ニューヨーク州など):
クラフトシードル/アップルワイン文化が非常に成熟しています。伝統的な辛口スティルから、オーク樽で熟成させたリッチなもの、ブドウのワイン(リースリングなど)とブレンドしたものまで、造り手の個性が爆発した、自由な発想のアップルワインに出会えます。
ラベルの読み方:「辛口」か「甘口」かを見極めよう
アップルワインを選ぶ際、一番失敗しないコツは「甘さのレベル」を確認することです。
-
辛口が飲みたい場合:
ラベルに「Dry」「Sec」「辛口」と書かれているものを選びましょう。
また、アルコール度数が「10%以上」あるものは、糖分がしっかりアルコールに変わっている(=辛口である)可能性が高いです。
-
甘口が飲みたい場合:
「Sweet」「Doux」「甘口」の表記を探します。
特に「Ice Cider」「氷結」「Late Harvest」などの表記があるものは、デザートワインとしての凝縮された甘みが期待できます。
ワイン好きのためのアップルワインの飲み方と最強ペアリング
さて、運命の1本を手に入れたら、いよいよそのポテンシャルを最大限に引き出す番です。
ここが、ワイン好きの腕の見せ所ですよ!
【最重要】「ワイングラス」で飲むこと!
シードルとの違いを決定づける、最大のポイントです。
アップルワインは、絶対に「ワイングラス」で飲んでください。
シードルのようにタンブラーやコップで飲んでしまうと、せっかくの複雑な香りが全く開かず、ただ「酸っぱいリンゴのお酒」で終わってしまいます。
-
おすすめグラス:
白ワイン用のグラス(シャルドネ用やリースリング用など、少し膨らみのあるもの)
-
温度:
白ワインと同じ。**しっかり冷やして(8℃〜12℃)**ください。
温度が低いうちはシャープな酸味を、グラスの中で温度が少し上がるにつれて、蜜や酵母の豊かな香りが開いてくる…という「変化」を楽しめるのも、スティルワインであるアップルワインならではの醍醐味です。
Manami的「黄金ペアリング」:豚肉料理は間違いない!
私が長野でアップルワインを飲んだ時、「これは絶対にアレと合う…!」と確信した料理があります。
それは「豚肉」です。
料理の世界でも「豚肉のリンゴソース添え」があるように、豚の脂の甘みと、リンゴの酸味・果実味は、古くから証明されてきた黄金の組み合わせ。
-
ポークソテー、サムギョプサル、とんかつ
豚の「脂」を、アップルワインの「シャープな酸」がスッキリと洗い流し、口の中をリセット。そして、リンゴの「果実味」が、豚肉の「旨味」をソースのように引き立てます。
これは、辛口のリースリングが豚肉と合うのと同じ理屈ですね。
-
ソーセージ、パテ・ド・カンパーニュ
加工肉の塩気やスパイス感とも相性抜群です。
-
鶏肉のロースト、クリームシチュー
豚肉だけでなく、鶏肉とももちろん合います。
また、カルボナーラやグラタンなど、クリーミーな料理にも、アップルワインの酸味が良いアクセントになってくれます。
チーズとのペアリング
ワインの友、チーズとも素晴らしい相性を見せます。
-
カマンベール、ブリー(白カビタイプ):
シードルの産地ノルマンディーがカマンベールの故郷でもあるように、リンゴと白カビチーズは鉄板。クリーミーな味わいに、リンゴの酸味が寄り添います。
-
コンテ、グリュイエール(ハードタイプ):
ナッツのようなコクのあるハードチーズの旨味と、アップルワインの果実味が同調します。
-
ブルーチーズ(甘口アップルワインと):
極甘口の「アイス・シードル」を手に入れたなら、ぜひ「ロックフォール」や「ゴルゴンゾーラ」と。貴腐ワインとブルーチーズに匹敵する、「甘じょっぱい」禁断のペアリングが楽しめます。
まとめ:白ワインの「新しい選択肢」へようこそ
シードルとは似て非なる、奥深い「アップルワイン」の世界、いかがでしたでしょうか。
-
アップルワインは、**「スティル(非発泡性)」で「アルコール度数が高い(10%以上)」**のが特徴。
-
それは、シードルが「爽快感」を目指すのに対し、アップルワインは「白ワインとしての骨格」を目指して造られるから。
-
味わいは、甘いジュースではなく、シャープな酸味が魅力の「辛口」が主流。
-
自家製は法律(酒税法)でNG。長野や青森の国産品や、カナダ産などを「買って」応援しよう。
-
飲むときは**「ワイングラス」で「しっかり冷やして」**。
-
豚肉料理やクリーミーな料理とのペアリングは、まさに黄金。
ブドウから造られる白ワインが、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリングと多様な個性を持つのと同じように、「リンゴ」という果実から造られる「スティルワイン」にも、独自の素晴らしい個性と可能性があります。
「今日は白ワインが飲みたいな」
そう思った時、いつものブドウのワインの隣に、この「アップルワイン」という新しい選択肢を加えてみませんか?
特に、ポークソテーや鶏肉のクリーム煮を食卓に並べる日。
キリッと冷やしたアップルワインをワイングラスに注げば、そのシャープな酸と豊かな果実味が、いつものディナーを格別なものにしてくれるはずです。
ぜひ、この「リンゴの白ワイン」が持つ、未知の美味しさに出会ってみてくださいね。