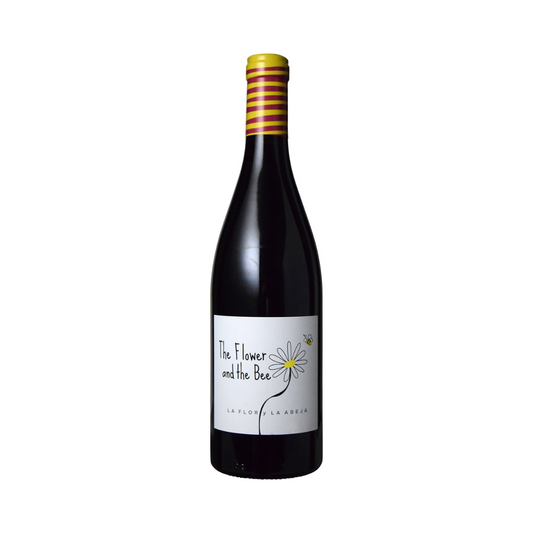こんにちは、CalivinoのManamiです。
突然ですが、あなたは最近、ワインショップやレストランのメニューで「オレンジワイン」という文字を見かけて、「これって一体何?」と首をかしげた経験はありませんか?
数年前、私もそうでした。友人と訪れたおしゃれなビストロで、ソムリエさんに「何か面白いワインを」とお願いしたところ、「では、こちらのオレンジワインはいかがでしょう?」と、夕焼けのような、美しいオレンジがかった液体がグラスに注がれたのです。
「え、オレンジ? オレンジから造ったワインですか?」
思わずそう聞いてしまった私に、ソムリエさんは優しく微笑んで「いえ、これは白ブドウから造るんですよ」と教えてくれました。一口飲んで、さらにびっくり。白ワインのようなフルーティーさもあるけれど、なんだか紅茶のような、ほんのりとした渋みと、奥深い「旨味」を感じる…。
それは、私が知っている白ワインとも赤ワインとも、ロゼワインとも全く違う、衝撃的な出会いでした。
ここ数年で一気にトレンドとなり、「第4のワイン」とも呼ばれるようになったオレンジワイン。でも、その名前のインパクトとは裏腹に、「実際どんな味なの?」「どうやって造るの?」「何と合わせたらいいの?」と、まだまだ謎に包まれた部分も多いですよね。
この記事では、そんなオレンジワインの魅力と謎を、ワイン好き30代女性の視点から、初心者の方にもわかりやすく、徹底的に解きほぐしていきます。
この記事を読み終える頃には、あなたはオレンジワインの基本をマスターし、自信を持って「次、あのオレンジワインを試してみよう!」と思えるようになっているはずです。知れば知るほど奥深い、この魅力的なワインの世界へ、一緒に出かけてみませんか?
オレンジワインとは?「第4のワイン」と呼ばれる理由
まず、オレンジワインの世界に足を踏み入れる前に、一番大切な基本の「キ」から押さえておきましょう。
誤解しないで!オレンジから作られているわけではありません
これが最大の誤解ポイントです! 私も最初は「オレンジ果汁を発酵させたお酒?」なんて思っていましたが、全く違います。
オレンジワインは、100%「ブドウ」から造られるワインです。
では、なぜあの美しいオレンジ色をしているのでしょうか? その秘密は、そのユニークな「造り方」にあります。
オレンジワインの正体:白ブドウを使った「赤ワインの造り方」
ワインの色は、どうやって決まるかご存知ですか?
すごくシンプルに言うと、こんな感じです。
-
白ワイン: 白ブドウの果汁だけを発酵させる。(皮や種はすぐに取り除く)
-
赤ワイン: 黒ブドウを、果実を丸ごと(皮や種も一緒に)発酵させる。
赤ワインのあの美しいルビー色やガーネット色は、黒ブドウの「皮」に含まれる色素(アントシアニン)が、発酵中に果汁に溶け出すことで生まれます。
さて、ここでオレンジワインです。
オレンジワインは、「白ブドウ」を使って、「赤ワインの造り方」で造られます。
つまり、通常ならすぐに取り除いてしまう白ブドウの「皮」や「種」も、果汁と一緒にタンクや樽(あるいは伝統的な甕)に入れて、数日間、長いものだと数ヶ月間も一緒に漬け込み、発酵させるのです。
なぜ「オレンジ」色になるの?
白ブドウの皮には、赤ワインになるほどの強い赤い色素はありません。しかし、ブドウの皮には「フラボノイド」や「カロテノイド」といった色素成分が微量に含まれています。
これらが長期間、果汁(アルコール)と触れ合うことで、じわじわと液体に溶け出します。その結果、ワインは黄金色から、琥珀(アンバー)色、そして鮮やかな「オレンジ色」に色づくのです。
同時に、皮や種からは「タンニン」と呼ばれる渋み成分や、複雑な香り、そして「旨味」成分も抽出されます。これが、オレンジワインのあの独特な味わいを生み出す鍵となります。
「アンバーワイン」や「ラマート」と呼ばれることも
オレンジワインという呼び名は、実は比較的最近、2000年代に入ってからイギリスのワイン商が使い始めた言葉だと言われています。
歴史的には、特に発祥の地とされるジョージアでは、伝統的にこの製法で造られるワインを「アンバーワイン(Amber Wine / 琥珀色のワイン)」と呼んできました。国際的な機関(O.I.V. - 国際ブドウ・ワイン機構)でも、このスタイルを正式に「アンバーワイン」としてカテゴリ分けする動きがあるようです。
また、イタリアのフリウリ地方などでは、ピノ・グリージョ(皮が少しピンクがかった白ブドウ)を使ってこの製法で造るワインを「ラマート(Ramato / 銅色の)」と呼ぶこともあります。
どれも基本的には同じ「白ブドウを皮ごと醸(かも)したワイン」を指す言葉だと覚えておくと良いでしょう。
オレンジワインの味と香りは?初心者が知っておきたい独特な風味
「理屈はわかったけど、結局どんな味なの?」
そうですよね、一番気になるのはそこだと思います。
オレンジワインの味わいを一言で表現するのは、実はとても難しいのです。なぜなら、白ワインの爽やかさ、赤ワインの骨格、そしてロゼとも違う独特の風味…そのすべてを併せ持つような、非常に「複雑」な味わいだからです。
白ワインでも赤ワインでもない、複雑な味わい
もしあなたが「白ワインはスッキリ、赤ワインはずっしり」というイメージを持っているなら、オレンジワインはそのどちらの枠にも収まりません。
-
白ワインの要素: リンゴや柑橘類のような果実味、きれいな酸味。
-
赤ワインの要素: 渋み(タンニン)、しっかりとした骨格、複雑な香り。
これらが一つの液体の中で見事に調和(あるいは個性的にぶつかり合って)います。
キーワードは「渋み」と「旨味」
オレンジワインの味わいを特徴づける最大のポイントは、間違いなく「渋み(タンニン)」と「旨味(うまみ)」です。
普通の白ワインでは、皮や種をすぐに取り除くため、渋みを感じることはほとんどありません。しかし、オレンジワインは皮や種と一緒に発酵させるため、赤ワインと同じようにタンニンが抽出されます。
ただし、その渋みは、重厚な赤ワインの「ガツン」とくる渋さとは少し違います。
例えるなら、**淹れたての緑茶や紅茶を飲んだ時に感じる、心地よい「渋み」や「苦味」**に近いです。これが口の中をスッキリさせてくれたり、味わいに立体感を与えてくれたりします。
そして、もう一つのキーワードが「旨味」。
皮や種、酵母などから溶け出すアミノ酸やミネラルが、出汁(だし)のような深い「旨味」となって舌に感じられます。これが、オレンジワインが「食中酒として万能」と言われる大きな理由の一つです(詳しくは後述します!)。
どんな香りがするの?(例:アプリコット、紅茶、ナッツ)
香りも非常に個性的です。
一般的な白ワインに多い、フレッシュなレモンやマスカットのような香りとは一線を画します。
オレンジワインによく感じられる香りの例を挙げてみましょう。
-
果実系: 熟したリンゴ、黄桃、アプリコット(特にドライアプリコット)、マーマレード、干し柿
-
花・ハーブ系: 金木犀(きんもくせい)、カモミール、オレンジピール、タイム
-
その他: 紅茶(アールグレイ)、ナッツ(アーモンド)、蜂蜜、スパイス、少し酸化的なニュアンス(シェリー酒や紹興酒のような)
これらの香りが幾層にも重なり合って、グラスを回すたびに違う表情を見せてくれるのが、オレンジワインの大きな魅力です。
私の初体験:衝撃的だった「旨味」との出会い
冒頭でお話しした、私が初めてオレンジワインを飲んだ時の話をもう少し。
ソムリエさんに「紅茶のような香りもしますよ」と言われ、半信半疑で香りを嗅ぐと、本当にアールグレイやドライアプリコットのような、甘く香ばしい香りがしました。
そして一口。
「……なにこれ!?」
まず感じたのは、しっかりとした果実味。でも、すぐに紅茶のような心地よい渋みが舌を包みました。そして飲み込んだ後に、じわーっと口の中に広がる「旨味」。
それはもう、ワインというより「上質な出汁」を飲んだかのような感覚でした。
「ワインで『旨味』を感じるって、こういうことか!」と、文字通り目からウロコが落ちる体験でした。
最初は少し戸惑うかもしれませんが、この「渋み」と「旨味」こそがオレンジワインのアイデンティティ。この魅力に気づくと、もう後戻りはできませんよ。
どうやって造られるの?オレンジワインの製法と歴史
このユニークなワインが、いつ、どこで、どのようにして生まれたのか。その背景を知ると、オレンジワインがさらに愛おしく、美味しく感じられるはずです。
「マセラシオン・カルボニック」じゃない!「醸し(かもし)」とは?
ワインの専門用語で、オレンジワインの製法(皮や種を果汁に漬け込むこと)を「マセラシオン(Maceration)」と呼びます。日本語では「醸(かも)し」と言います。
(※似た言葉に「マセラシオン・カルボニック」という、ボジョレー・ヌーヴォーなどで使われる製法がありますが、これは全く別物なのでご注意を!)
赤ワインもオレンジワインも、この「醸し」を行うワインです。
オレンジワインの個性を決めるのは、まさにこの「醸し」の期間。
-
数日間(短い): 色は淡いオレンジ色。渋みは穏やかで、フルーティーさが残る、初心者にも飲みやすいスタイル。
-
数週間~数ヶ月(長い): 色は濃い琥珀色。渋みも旨味もしっかりと抽出され、非常に複雑で個性的な味わい。
造り手さんが「どんなオレンジワインにしたいか」によって、この醸しの期間を調整しているのです。
オレンジワインの作り方:白ワインとの決定的な違い
ここで、白ワインとオレンジワインの製造工程を、ざっくり比較してみましょう。
【一般的な白ワイン】
-
収穫(白ブドウ)
-
圧搾(すぐに搾る) ← ★ココが違う!
-
発酵(果汁だけ)
-
熟成
-
瓶詰め
【オレンジワイン】
-
収穫(白ブドウ)
-
破砕(実を軽く潰す)
-
発酵(皮・種ごと) & 醸し ← ★ココが違う!
-
圧搾(発酵後に搾る)
-
熟成
-
瓶詰め
つまり、「先に搾る」か「後で搾る」か。この順番の違いが、白ワインとオレンジワインを分ける決定的なポイントなのです。
発祥の地はジョージア!8000年の歴史と「クヴェヴリ」
オレンジワインは「最近のトレンド」と思われがちですが、実はその歴史、なんと8000年にも遡ると言われています。
その発祥の地は、ロシアとトルコに挟まれたコーカサス地方の国、ジョージア(昔はグルジアと呼ばれていましたね)。ジョージアは「ワイン発祥の地」とも言われており、まさにワインの故郷のような場所です。
ジョージアでは、古来から「クヴェヴリ(Qvevri)」と呼ばれる、卵型をした巨大な素焼きの甕(かめ)を使った伝統的なワイン造りが行われてきました。
このクヴェヴリを地中に埋め、収穫した白ブドウを皮や種、時には梗(ブドウの軸)まで丸ごと入れ、自然の力(野生酵母)で発酵させ、そのまま数ヶ月間「醸し」と「熟成」を行います。
地中に埋めるのは、年間を通じて温度を一定に保つため。素焼きの甕は、現代のステンレスタンクとは違い、ごくわずかに呼吸をするため、ワインに独特の複雑味とまろやかさをもたらします。
この8000年続くジョージアの伝統的なクヴェヴリ製法は、2013年にユネスコの無形文化遺産にも登録されました。私たちが今「新しい!」と熱狂しているオレンジワインは、実は人類最古のワインの姿の一つだった、ということ。なんだかロマンがありますよね。
なぜ今、世界中でブームになっているの?
この伝統的な製法が、なぜ今、世界的なブームになっているのでしょうか?
きっかけは、イタリアのフリウリ地方(スロヴェニア国境沿い)の造り手たちが、1990年代にこのジョージアの伝統製法に光を当て、自分たちの土地で復活させたことだと言われています。
彼らの造る個性的でパワフルなオレンジワインが、世界中のソムリエやワイン愛好家の間で話題となりました。
さらに、近年の「自然派ワイン(ナチュラルワイン)」ブームが、その人気を決定的なものにしました。
自然派ワインの造り手たちは、「できるだけ人の手を加えない、ブドウ本来の力を引き出す」ことを目指します。皮や種に含まれる天然の抗酸化成分(タンニンやポリフェノール)を利用するオレンジワインの製法は、酸化防止剤(亜硫酸塩)の使用を最小限に抑えたい彼らの哲学と、まさに合致したのです。
こうして、ジョージアやイタリアだけでなく、フランス、スペイン、オーストリア、そしてここ日本でも、たくさんの造り手さんが素晴らしいオレンジワインを造るようになり、私たち消費者の目にも触れる機会が爆発的に増えた、というわけです。
オレンジワインと料理のペアリング術:食卓が劇的に変わる魔法
さて、オレンジワインの魅力がわかってきたところで、次は一番実用的なお話、「何と合わせて食べるか?」です。
断言します。**オレンジワインは、「ペアリングの救世主」**です。
ワインと料理を合わせることを「ペアリング」や「マリアージュ(結婚)」と呼びますが、これがなかなか難しい。
「この料理、白ワインだとちょっと物足りない。でも、赤ワインだと強すぎる…」
そんな「ペアリングの隙間」に、オレンジワインは完璧にフィットしてくれるんです。
万能選手!オレンジワインが「ペアリングの救世主」と呼ばれる理由
なぜオレンジワインが万能なのか?
それは、これまで説明してきた「味わいの要素」を思い出せば簡単です。
-
白ワインの「酸」:料理の油分を洗い流し、爽やかさをもたらす。
-
赤ワインの「渋み(タンニン)」:肉や脂の旨味と結びつき、味わいにコクを与える。
-
独特の「旨味」:発酵食品や出汁(だし)といった、日本人の味覚に響く要素と共鳴する。
-
複雑な「香り」:ハーブやスパイスの風味を引き立てる。
これらすべてを併せ持つため、守備範囲がとんでもなく広いのです。
白ワインが苦手とするようなクセのある食材(例:青魚、野菜の苦味)も、赤ワインが合わせにくい繊イスな料理(例:白身魚の煮付け)も、オレンジワインなら両方受け止めてくれます。
具体的なおすすめペアリング:和食からエスニックまで
「本当に?」と思う方のために、具体的なペアリング例をご紹介します。
これを試せば、あなたもオレンジワインの虜になること間違いなしです!
和食(お寿司、煮物、ぬか漬け)との意外な相性
「和食にワイン」というと、繊細な白ワインを合わせることが多いですよね。でも、実はオレンジワインこそ、最強のパートナーかもしれません。
-
お寿司・お刺身: 特にコハダやサバ、アジなどの「青魚(光り物)」。白ワインだと生臭さが出てしまうことがありますが、オレンジワインの適度な渋みが、魚の脂と生臭さをキュッと引き締め、旨味に変えてくれます。
-
煮物(きんぴらごぼう、筑前煮): 醤油やみりんを使った甘辛い味付けと、オレンジワインの持つドライフルーツのような果実味、そして「旨味」が驚くほど同調します。
-
発酵食品(ぬか漬け、味噌、納豆): これはもう、鉄板です。ワイン自体が持つ発酵のニュアンスや旨味が、同じ発酵食品である漬物や味噌と見事に調和します。ぬか漬けで一杯、なんていう粋な楽しみ方ができるのも、オレンジワインならでは。
中華料理・エスニック料理(スパイス料理)との最強タッグ
私がオレンジワインにドハマりしたきっかけの一つが、これです。
スパイスやハーブ、複雑な調味料が使われるアジア料理は、ワインペアリングの難易度が非常に高いジャンル。
-
中華料理: 餃子(特に皮の香ばしさと酢醤油)、麻婆豆腐、青椒肉絲(チンジャオロース)。程よい渋みが中華の油を切り、紹興酒を合わせるような感覚で楽しめます。
-
エスニック料理(タイ、ベトナム): パクチーやレモングラス、ナンプラーを使った料理(グリーンカレー、生春巻き、トムヤムクンなど)。オレンジワインの持つハーブやスパイスの香りが、料理の香りを邪魔せず、むしろ引き立て合い、高め合います。
-
スパイス料理: クミンやコリアンダーを使ったカレーやタンドリーチキン。スパイシーさを、オレンジワインの果実味とタンニンが優しく受け止めてくれます。
チーズやナッツ、ドライフルーツと
もちろん、王道の組み合わせも得意です。
-
チーズ: フレッシュなものより、ウォッシュタイプやハードタイプ、シェーブル(山羊)など、少しクセのあるチーズと相性抜群です。
-
ナッツ類: アーモンドやクルミ。ワインの香ばしいナッツの香りとリンクします。
-
ドライフルーツ: 特にアプリコットやイチジク。これはもう、言わずもがなですね。
私のおすすめ!「キムチ鍋とオレンジワイン」の意外なマリアージュ
ここで、私の個人的なおすすめを一つ。
それは、冬の定番「キムチ鍋」です!
「え、キムチ鍋にワイン? しかもオレンジ?」と驚かれるかもしれません。
私も最初は遊び心で試してみたんです。ある寒い日、家でキムチ鍋をつつきながら、飲みかけのオレンジワインを合わせてみました。
…これが、衝撃的な美味しさでした。
キムチの酸味と発酵の旨味、唐辛子の辛さ、豚肉や魚介の出汁…。
これだけ要素が複雑な料理に、普通のワインはまず太刀打ちできません。
しかし、オレンジワインは違いました。
-
ワインの「旨味」が、鍋の「出汁の旨味」と共鳴し、
-
ワインの「酸」が、キムチの「酸味」と手を取り合い、
-
ワインの「渋み」が、豚肉の「脂」をさっぱりとさせ、
-
ワインの「果実味」が、唐辛子の「辛さ」を優しく包み込む…!
まさに、すべての要素がカチッとハマる感覚でした。
「ああ、オレンジワインって、本当に懐が深い…!」と感動したのを覚えています。
騙されたと思って、ぜひ一度試してみてください。あなたの食卓の常識が変わるかもしれませんよ。
初心者向け!オレンジワインの選び方と美味しい飲み方
「オレンジワイン、試してみたくなった! でも、どうやって選べばいいの?」
「美味しく飲むためのコツは?」
最後は、そんなあなたの背中を押す、実践的なアドバイスです。
最初の1本はどう選ぶ?ラベルで注目すべきポイント
オレンジワインは、その製法上、造り手の個性が出やすく、味わいの振り幅がとても広いワインです。中には、かなりマニアックで「上級者向け」な味わいのものもあります。
初心者が最初の1本で「うっ…個性的すぎる…」と挫折しないために、選び方のコツをお教えします。
1. 「醸し(マセラシオン)の期間」をチェック!
もし可能なら、ショップの店員さんに「醸しの期間が短いもの」を選んでもらいましょう。
期間が短い(数日~2週間程度)ものは、色が淡く、渋みも穏やかで、白ワイン寄りのフルーティーさが残っていることが多いです。まずはこのタイプから入るのがおすすめ。
逆に、数ヶ月単位で醸したものは、色が濃く、渋みも旨味も強烈な、個性派タイプが多いです。
2. 色の濃さで判断する
ボトルの色を見てみましょう。透明なボトルの場合、
-
淡いオレンジ色、ピンクゴールドに近い色: おそらくライト~ミディアムボディ。飲みやすい可能性が高いです。
-
濃いオレンジ色、茶色がかった琥珀色: 濃厚で複雑、渋みもしっかりしている可能性が高いです。
3. 価格帯で選ぶ
オレンジワインは製法に手間がかかることもあり、極端に安いものは少ない傾向にあります。まずは3,000円~5,000円くらいの価格帯で探してみると、品質と個性のバランスが良いものに出会える確率が高いです。
産地で選ぶ(ジョージア、イタリア、日本)
産地で選ぶのも一つの手です。
-
イタリア(特にフリウリ地方): オレンジワインの「モダンな」火付け役。洗練されていて、果実味と複雑味のバランスが良いものが多いです。
-
ジョージア: 発祥の地。クヴェヴリで造られた伝統的なスタイルは、非常に個性的でパワフル。紅茶や干し柿のような風味が強く、旨味もたっぷりです。最初は少し驚くかもしれませんが、ハマると抜け出せない魅力があります。
-
日本: 日本の「甲州」という白ブドウは、皮に色素や旨味成分を多く含むため、オレンジワイン(甲州グリ・ド・グリなどと呼ばれます)に最適です。和食に寄り添う、繊細で旨味のあるオレンジワインが多く、日本人には一番しっくりくるかもしれません。
オレンジワインの適温は?冷やしすぎはNG!
これは非常に重要なポイントです!
オレンジワインは、冷やしすぎないでください!
白ワインの感覚で、冷蔵庫でキンキンに冷やしてしまうと、どうなるか?
せっかくの豊かな香り(金木犀やアプリコットなど)が閉じてしまい、渋み(タンニン)だけがギスギスと際立って、「苦くて美味しくない」と感じてしまいます。
おすすめの温度は、**「白ワインよりは高く、赤ワインよりは低い」**温度帯。
具体的には、12℃~16℃くらいです。
-
冷蔵庫から出してすぐ(5℃前後) → 冷えすぎです!
-
冷蔵庫から出して、室温で30分~1時間ほど置いたくらい → ちょうど良い◎
-
あるいは、野菜室で保管(10℃前後)しておき、飲む少し前に出す。
少し高めの温度で飲むことで、香りが華やかに開き、渋みもまろやかに感じられ、本来の美味しさを楽しむことができます。
どんなグラスで飲むべき?
グラスは、一般的な白ワイングラスで大丈夫です。
もし、赤ワイン用の大ぶりなブルゴーニュグラスがあれば、そちらで試してみるのも面白いですよ。複雑な香りがより一層立ち上り、リッチな気分を味わえます。
よくある質問と豆知識
最後に、オレンジワインに関してよく聞かれる質問や、知っておくとちょっと通ぶれる豆知識をまとめました。
Q: オレンジワインは「自然派ワイン(ナチュラルワイン)」なの?
A: 「イエス」でもあり「ノー」でもあります。
オレンジワインの製法(皮ごと醸す)は、天然の抗酸化作用を利用するため、酸化防止剤を減らしたい自然派ワインの造り手に好まれる傾向があります。そのため、結果的に「オレンジワイン=自然派ワイン」である確率は高いです。
しかし、「オレンジワイン」はあくまで「製法・スタイル」を指す言葉。「自然派ワイン」は「栽培や醸造の哲学」を指す言葉です。
自然派ではない造り手がオレンジワインを造ることもあれば、その逆もまた然り。イコールではない、と覚えておきましょう。
Q: ロゼワインとの違いは?
A: 「原料ブドウ」と「製法」が逆です!
-
オレンジワイン: 「白ブドウ」を「赤ワイン」のように造る(皮と種を長く漬け込む)。
-
ロゼワイン: 「黒ブドウ」を「白ワイン」のように造る(皮と種を短時間だけ漬け込む、または黒ブドウと白ブドウを混ぜるなど)。
原料も目的も全く違う、別カテゴリーのワインです。
Q: どこで買える?ワインショップでの見つけ方
A: 数年前に比べると、格段に見つけやすくなりました。
普通の酒屋さんやスーパーではまだ少ないかもしれませんが、「ワイン専門店」や「自然派ワインに強いショップ」に行けば、ほぼ確実に出会えます。
ショップの棚では、「白ワイン」のコーナーの端や、「ロゼワイン」の近く、あるいは「ジョージア」や「イタリア・フリウリ」といった産地別コーナー、もしくは「自然派ワイン」コーナーに置かれていることが多いです。
見つからなければ、勇気を出して店員さんに「オレンジワイン、ありますか?」と聞いてみましょう。きっと親切に教えてくれるはずです。
Q: 健康や美容に良いって本当?
A: 期待できるかもしれません!
赤ワインが健康に良いとされる理由の一つに、皮や種に含まれる「ポリフェノール」(タンニンやアントシアニンなど)の抗酸化作用がありますよね。
通常の白ワインは、皮や種をすぐに取り除いてしまうため、この恩恵が少ないのですが…
もうお分かりですね。
オレンジワインは、白ブドウの皮や種をしっかりと漬け込んで造ります。そのため、白ワインでありながら、赤ワインのようにポリフェノールを豊富に含んでいるのです。
美味しく飲んで、美容や健康にも少し良い影響があるかもしれない、と思うと、なんだか嬉しくなっちゃいますね(もちろん、飲み過ぎは禁物ですが!)。
まとめ:オレンジワインの世界へようこそ
さて、ここまで「第4のワイン」、オレンジワインの魅力について、本当に基礎の基礎から、ちょっとマニアックな歴史、そして実践的なペアリング術まで、私の体験談も交えながら熱く語ってまいりました。
もう一度、大切なポイントをおさらいしましょう。
-
オレンジワインは、オレンジからではなく**「白ブドウ」**から造られる。
-
製法は、白ブドウの**皮や種と一緒に「醸す(かもす)」**という赤ワインに近い造り方。
-
味わいの特徴は、白や赤にはない**「渋み」と「旨味」**。
-
香りは、アプリコットや紅茶、ナッツのように複雑で芳醇。
-
歴史は古く、**ジョージアの「クヴェヴリ」**製法がルーツ。
-
ペアリングは超万能! 特に和食や中華、エスニックと相性抜群。
-
飲むときは、**「冷やしすぎない」**のが鉄則!
最初は、その独特の渋みや香りに少し戸惑うかもしれません。でも、その一口目の「?」が、二口目、三口目で「!」に変わり、気づけばその奥深い魅力にどっぷりとハマっている…。それがオレンジワインです。
白ワインの気軽さと、赤ワインの奥深さ。その両方をいいとこ取りしたような、懐の深いオレンジ色の液体は、あなたの食卓を、そしてワインライフを、間違いなくもっと豊かでエキサイティングなものにしてくれます。
まずは難しく考えず、今日のディナーのお供に、一本選んでみませんか?
和食にも、中華にも、いつもの家庭料理にも、きっと優しく寄り添ってくれるはずです。
ぜひ、あなたの「推し」オレンジワインを見つけてみてください。
そして次の女子会やディナーで、「このワイン、実は白ブドウの皮で造っててね…」なんて、この奥深いオレンジ色の魅力について語ってみませんか?
あなたのワインの世界が、さらに広がることを願っています!