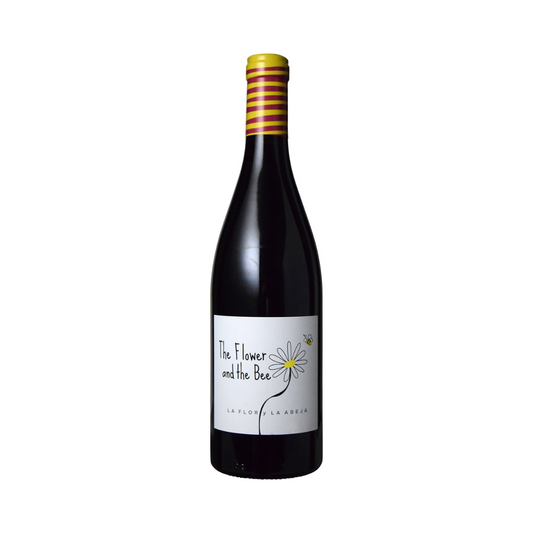こんにちは、CalivinoのManamiです。
突然ですが、あなたは「シードル」と聞いて、どんなイメージをお持ちですか?
「リンゴの甘いお酒でしょ?」
「カフェのランチで、ガレットと一緒に飲むおしゃれなドリンク」
「アルコールが低いから、ちょっと物足りないかも…」
数年前まで、私も全く同じイメージでした。ワインに夢中だった私にとって、シードルは「ワインやビールの代わりにはならない、ちょっと可愛い、甘めの発泡ジュース」くらいの認識だったんです。
そのイメージが180度変わったのは、行きつけのビストロでのこと。
いつものように白ワインを頼もうとしたら、ソムリエさんに「Manamiさん、今日はすごく良いシードルが入ったんですが、騙されたと思って飲んでみませんか?」と声をかけられました。
「え、シードルですか? 食事に?」
半信半疑の私に出てきたのは、ビールジョッキではなく、なんと「ワイングラス」に注がれた、淡い黄金色の液体。泡立ちも、シャンパンのように繊細です。
恐る恐る香りを嗅いでみると…
「……え、なにこれ!?」
私が知っている「甘いリンゴジュース」の香りじゃない。
確かにリンゴの蜜のような香りはするけれど、それだけじゃない。まるでブルゴーニュの白ワインのような、少しトーストしたナッツや酵母の、複雑で香ばしい香りが立ち上るんです。
一口飲んで、さらに衝撃が走りました。
「辛口!?」
甘さはほとんど感じず、キリッとした酸味と、ほのかに紅茶のような「渋み」。そして、喉を通った後に鼻に抜ける、リンゴの華やかな香り。
「これ、本当にあのシードルなの…?」
その日、私が合わせたのは豚肉のロースト。シードルの爽やかな酸味が豚の脂をスッと流し、リンゴの果実味がソースのように肉の旨味を引き立てて…。まさに完璧なマリアージュでした。
ワイン好きの私が、なぜ今、シードルにもこんなに夢中になっているのか。
それは、シードルが**「ビールより優雅で、ワインより気軽」、そして「食中酒として無限の可能性を秘めている」**ことに気づいてしまったからです。
この記事では、かつての私のように「シードル=甘いお酒」と誤解しているあなたへ、その奥深く、多様性に満ちた世界を、ワイン好きの視点から徹底的に解き明かしていきます。
この記事を読み終える頃には、あなたはシードルが「リンゴから造られる、もう一つのワイン」であることに気づき、今夜の食卓のパートナーとして選んでみたくてたまらなくなっているはずです。
シードルとは?「リンゴのワイン」と呼ばれる基本の「キ」
まずは、シードルの基本定義から押さえていきましょう。知っているようで意外と知らない、その正体とは?
シードルの定義:リンゴ100%で造られる醸造酒
シードルとは、ひと言でいえば**「リンゴ果汁をアルコール発酵させたお酒」**です。
原料は、100%リンゴ。ブドウから造れば「ワイン」になるのと同じで、リンゴから造るから「シードル」と呼ばれる、とてもシンプルな醸造酒です。
炭酸ガスを含んだ「発泡性」のものが一般的ですが、ワインと同じように、泡のない「非発泡性(スティル)」のシードルも存在します。
よく「リンゴのワイン」とも呼ばれるのは、この製造工程がワインと非常によく似ているからです。果実を搾り、その糖分を酵母の力でアルコールに変える。まさに、自然の恵みをそのまま活かしたお酒なのです。
「シードル」「サイダー」「ハードサイダー」の違いとは?
ここで、ややこしい「呼び名」の問題を整理しておきましょう。
-
シードル (Cidre):
フランス語の呼び名です。日本ではこの呼称が最も一般的ですね。特に、フランスのブルターニュ地方やノルマンディー地方で造られる、伝統的なスタイルを指すことが多いです。
-
サイダー (Cider):
英語の呼び名です。主にイギリスや、かつてイギリスの植民地だった国々(アメリカ、カナダ、オーストラリアなど)で使われます。
-
【要注意!】日本の「サイダー」との違い
私たち日本人が「サイダー」と聞くと、三ツ矢サイダーのような「甘い炭酸飲料(ノンアルコール)」を思い浮かべますよね。これは、明治時代にイギリスから「Cider」が伝わった際、なぜかノンアルコールの炭酸飲料の商品名として広まってしまったため、と言われています。
海外で「Cider」を頼むと、基本的にお酒が出てくるので注意しましょう。
-
ハードサイダー (Hard Cider):
主にアメリカで使われる言葉です。アメリカでは、単に「Cider(サイダー)」というと、ノンアルコールの濁ったリンゴジュース(アップルサイダー)を指すことが多いため、それと区別するためにアルコール入りのものを「ハード(アルコールが強い)サイダー」と呼びます。
この記事では、日本で最も馴染みのある「シードル」という呼称で統一していきますね。
アルコール度数はどれくらい?ワインやビールとの比較
シードルの大きな魅力の一つが、そのアルコール度数の幅広さです。
一般的なアルコール度数は2%〜8%程度。
-
フランス産(特に甘口)
:2%〜4%と、非常に低め。
-
イギリス産やアメリカ産
:5%〜8%と、ビールに近いか、それ以上。
ワインのアルコール度数が平均12%〜14%なのと比べると、かなりライトですよね。
「ワインを1本開けるのは重いけど、ビールほどカジュアルすぎないお酒が飲みたい」
そんな、私たち30代女性のわがままな(笑)ニーズに、シードルは完璧に応えてくれるんです。
なぜ今、世界中で「クラフトシードル」がブームなのか?
ここ数年、世界的に「クラフトシードル」ブームが起きています。クラフトビールやナチュラルワイン(自然派ワイン)に続く、新しい波として注目されているんです。
その背景には、いくつかの理由があります。
-
グルテンフリー需要の高まり
ビールは麦(グルテン)から造られますが、シードルはリンゴ100%。グルテンフリーを志向する人にとって、ビールに代わる素晴らしい選択肢となりました。
-
健康志向(低糖質・低カロリー)
カクテルや甘いRTD(缶チューハイなど)に比べ、特に辛口のシードルは糖質が低く、カロリーも控えめ。リンゴ由来のポリフェノールも摂取できるとあって、健康志"舌"の肥えた層に選ばれています。
-
「クラフト」文化の成熟
クラフトビールやクラフトジンのブームを経て、消費者が「大量生産品ではない、造り手の顔が見える、個性的なお酒」を求めるようになりました。シードルもその流れに乗り、小規模な醸造所(サイダリーと呼びます)が世界中で増えています。
-
ナチュラル志向
ナチュラルワインと同様に、農薬を使わずに育てたリンゴを使い、野生酵母で発酵させ、酸化防止剤(亜硫酸塩)を無添加、あるいは最小限に抑えた「ナチュラルシードル」が、特に感度の高い人々の間で人気を集めています。
シードルはどう造られる?ワインとの違いと共通点
「リンゴのワイン」と呼ばれるシードルですが、その製造工程には、ワインと似ている部分と、全く異なる部分があります。この違いを知ると、シードルの味わいがより深く理解できますよ。
原料は「リンゴ」。でも、食用の「ふじ」や「つがる」とは違う?
これが、シードルの味わいを決定づける最大の秘密かもしれません。
本格的なシードルは、私たちが普段スーパーで買っている「ふじ」や「ジョナゴールド」のような、甘くてジューシーな「食用リンゴ」だけでは造られません。
もちろん、食用リンゴからでもシードルは造れます(日本のシードルは食用リンゴを使うことが多いです)。
しかし、ヨーロッパの伝統的なシードル産地(フランスやイギリス)では、「シードル専用品種」のリンゴが使われます。
このシードル専用品種、そのままかじってみると…
「にがっ!」「しぶっ!」「酸っぱすぎ!」
と、とても生では食べられないような、強烈な個性を持っています。
これらの品種は、味わいの特性によって大きく4つに分類されます。
-
Sweet(甘い):糖度が高い
-
Bittersweet(甘苦い):糖度も渋みも高い
-
Bittersharp(苦酸っぱい):渋みも酸味も高い
-
Sharp(酸っぱい):酸味が非常に高い
食用のリンゴは、基本的に「甘い」か「甘酸っぱい」ですよね。
しかし、シードル造りでは、特に**「Bittersweet(甘苦い)」や「Bittersharp(苦酸っぱい)」**の品種が非常に重要視されます。
なぜなら、この「渋み(タンニン)」こそが、シードルにワインのような「骨格」や「複雑味」、そして「長期熟成の可能性」を与えてくれるからです。
伝統的な産地では、これらの特性の違う数十種類のリンゴをブレンドすることで、毎年安定した、複雑な味わいのシードルを生み出しているのです。
シードルの製造工程をシンプルに解説
では、あのシワシワで渋いリンゴが、どうやって美味しいシードルになるのでしょうか?
工程はワインととてもよく似ています。
-
収穫 (Harvesting)
リンゴの木から収穫します。完熟して自然に落ちたリンゴを拾う、伝統的な方法もあります。
-
破砕 (Grinding)
リンゴを丸ごと、あるいはカットして、細かくすり潰します。昔ながらの水車を使った石臼で潰すところも。
-
圧搾 (Pressing)
すり潰したリンゴ(パルプ)を、プレス機でゆっくりと搾り、果汁(ジュース)を取り出します。
-
発酵 (Fermentation)
果汁をタンク(ステンレスや木樽)に入れます。すると、リンゴの皮についていた野生酵母、あるいは培養酵母が、果汁の中の「糖分」を食べて、「アルコール」と「炭酸ガス」に分解し始めます。これがアルコール発酵です。
-
熟成 (Maturation)
発酵が終わった後、そのまま数ヶ月から数年、タンクや木樽で熟成させ、味わいを落ち着かせます。
-
瓶詰め (Bottling)
最後に瓶詰め。この時、どうやって「泡」を加えるかで、いくつかのスタイルに分かれます。
-
瓶内二次発酵:シャンパンと同じ。瓶詰め後に糖分と酵母を加え、瓶の中で再度発酵させて泡を閉じ込める。きめ細かく、持続性のある泡になる。
-
シャルマ方式:大きな密閉タンクの中で二次発酵させる。
-
炭酸ガス注入:出来上がったシードルに、後から炭酸ガスを吹き込む。
-
私の体験談:日本のサイダリー(醸造所)訪問
数年前、ワイン好きの友人と、リンゴの名産地である長野県のシードル醸造所(サイダリー)を訪れたことがあります。
ワイナリー(ワイン醸造所)は見慣れていましたが、サイダリーは初めて。
扉を開けた瞬間、ブドウとは全く違う、甘酸っぱくて芳醇な「リンゴ」の香りに包まれて、それだけで幸せな気分になりました。
そこで造り手の方に伺った話が、まさに目からウロコでした。
「うちはフランスのシードル専用品種も育てているけど、メインは日本の『ふじ』や『紅玉』なんです」
「え、食用リンゴでも美味しくなるんですか?」
「なりますよ。でも、ワインと同じで『テロワール』が命です。この土地の寒暖差が、ふじにしっかりとした酸味と蜜を与えてくれる。その個性をどう引き出すかが、僕らの仕事です」
ワイン造りと同じ情熱、同じ哲学が、そこにはありました。
「リンゴもブドウと同じ、農作物なんだ」
そう実感してから、シードルを見る目が完全に変わりました。グラスの中の液体が、畑の風景や造り手の顔と結びついた瞬間でした。
甘口から辛口まで!シードルの「味わい」タイプ別ガイド
シードルが敬遠される理由の多くは、「甘い」というイメージです。
でも、実際にはビールのラガーとスタウトくらい、味わいの幅があります。ラベルの表記を理解すれば、好みの1本に必ず出会えますよ。
ラベルでよく見る「甘さ」の表記を知ろう
特にフランス産のシードルには、甘さのレベルが明記されていることが多いです。これはシャンパンの表記と似ていますね。
-
ブリュット (Brut / Dry) = 辛口
発酵で糖分のほとんどがアルコールに変わった、甘さが最も少ないタイプ。キリッとした酸味とドライな飲み口が特徴です。
-
ドゥミ・セック (Demi-Sec / Semi-Dry) = 中辛口(やや甘口)
「ドゥミ」はフランス語で「半分」の意味。ほんのりとリンゴの甘みを残したスタイル。フルーティーさと飲みやすさのバランスが良いです。
-
ドゥー (Doux / Sweet) = 甘口
発酵を途中で止めるなどして、リンゴの甘みをたっぷりと残したタイプ。アルコール度数も低め(2〜4%)で、デザート感覚や食前酒に最適です。
Manami的おすすめは断然「辛口(ブリュット)」!
もしあなたが「シードルって、ちょっと子供っぽい味だよね」と思っているなら、絶対に「ブリュット(辛口)」から試してみてください!
私がビストロで衝撃を受けたのも、このブリュットでした。
リンゴの香りはしっかりするのに、味わいはドライ。
ビールのようにゴクゴク飲める爽快感と、白ワインのような複雑味や(専用品種を使ったものなら)渋みが両立しています。
「甘いお酒はちょっと苦手…」という方や、ビール党の男性にも「これならウマい!」と言わせる力があるのが、辛口シードルです。
特に、後述する「食事とのペアリング」において、主役となるのは間違いなくこのタイプです。
「にごり」シードルと「クリア」なシードル
味わいは、甘さだけでなく「見た目」にも左右されます。
-
クリアなタイプ (Filtered)
瓶詰め前にしっかりと濾過(ろか)されたもの。雑味がなく、スッキリと洗練されたクリーンな味わいです。黄金色が美しく、泡立ちも綺麗に見えます。
-
にごりタイプ (Unfiltered)
あえて濾過をしない、あるいは最小限に抑えたもの。「クラフトシードル」や「ナチュラルシードル」に多いスタイルです。
リンゴの果実そのものの旨味や、発酵由来の酵母の風味が残り、非常に複雑で飲みごたえのある味わいになります。見た目は少し濁っていますが、この「旨味」こそが、発酵食品(チーズや味噌など)とのペアリングで真価を発揮します。
シードルの二大巨頭!フランスとイギリス、産地別特徴
シードルの世界を牽引するのは、フランスとイギリス。この二大産地の違いを知ると、シードル選びが格段に楽しくなります。
フランス (Cidre) の特徴:優雅さと気品、食中酒の王道
フランスのシードルは、まさに「リンゴのワイン」と呼ぶにふさわしい、エレガントなスタイルが特徴です。
-
代表産地: ノルマンディー地方、ブルターニュ地方
-
特徴:
-
シードル専用品種(渋みや苦味のあるリンゴ)を数十種類ブレンドして造るのが伝統。
-
アルコール度数は低め (2%〜5%)。
-
製法は、シャンパンと同じ「瓶内二次発酵」で造られる高品質なものも多い。
-
-
味わい:
アルコールが低い分、リンゴの華やかな香りが際立ちます。そして最大の特徴は、専用品種由来の豊かなタンニン(渋み)。この渋みが味わいに骨格を与え、食事(特に肉料理やチーズ)と合わせた時に力を発揮します。
イギリス (Cider) の特徴:伝統と多様性、パブの主役
イギリスは、世界で最もシードルを愛し、最も多く消費している国。生活に密着した、多様なスタイルが特徴です。
-
代表産地: サマセット州、ヘレフォードシャー州
-
特徴:
-
パブでビールと同じように「パイントグラス」で飲む文化が根付いています。
-
アルコール度数はフランス産より**高め (5%〜8%)**で、しっかりした飲みごたえ。
-
辛口(ドライ)が主流。
-
-
味わい:
フランス産のような華やかさよりは、リンゴの力強さや、時には木樽由来のスモーキーな香りを感じるものも。
伝統的な「スクランピー (Scrumpy)」と呼ばれるスタイルは、無濾過でアルコール度数も高く(8%を超えることも)、非常に個性的でパワフルな味わいです。
世界に広がるシードルの個性:スペイン、アメリカ、そして日本
二大巨頭以外にも、魅力的なシードルを造る国はたくさんあります。
-
スペイン (Sidra / シドラ)
アストゥリアス地方が有名。最大の特徴は、泡がない(スティル)か微発泡であることと、リンゴ酢のように強烈に酸っぱいこと!
「エスカンシアール」と呼ばれる、ボトルを頭上高くに掲げ、グラスを腰の位置で受けて、高い位置から注ぎ落とす独特な飲み方(パフォーマンス)も有名です。これは、空気に触れさせて香りを立たせ、一時的に泡立たせるため。
-
アメリカ (Hard Cider)
クラフトビール人気と連動し、爆発的に醸造所が増加。伝統に縛られない、自由な発想が魅力です。ホップを加えてビールのように仕上げた「ホップド・サイダー」や、ベリー、生姜などを加えたフレーバータイプも人気です。
-
日本 (シードル)
長野県や青森県など、リンゴの名産地で、非常に高品質なシードルが急増しています。
特徴は、私たちが食べ慣れた「ふじ」や「紅玉」といった食用リンゴをメインに使うこと。そのため、ヨーロッパ産のような強い渋みは少なく、繊細でクリーン、フルーティーな味わいのものが多く、日本人の味覚や和食にも合わせやすいのが魅力です。
シードルの真価!食中酒としての最強ペアリング術
さあ、ここからが本題です。
私がシードルにハマった最大の理由、それは「食中酒としての万能性」です。ワインが合わせにくい料理にも、ビールのようカジュアルに寄り添ってくれます。
なぜシードルはこんなにも食事に合うのか?
シードルが万能な理由は、4つの要素をバランス良く持っているからです。
-
爽やかな「酸味」:料理の脂っぽさをリフレッシュさせ、口の中を洗い流してくれます(唐揚げやフライドポテトに最高!)。
-
ほのかな「果実味」:料理の甘みや、スパイスの風味と優しく調和します(エスニック料理や甘辛い和食に!)。
-
心地よい「発泡」:油分をリセットし、次のひと口を新鮮に感じさせてくれます。
-
(特にフランス産)「渋み(タンニン)」:赤ワインのように、肉の脂やチーズのタンパク質と結びつき、旨味を増幅させます。
【鉄板ペアリング】ガレットとシードル(ブルターニュ風)
まずは、王道中の王道から。フランス・ブルターニュ地方の郷土料理「ガレット」です。
そば粉のクレープであるガレットの香ばしい風味、ハムやベーコンの塩気、卵のまろやかさ、チーズ(グリュイエールなど)のコク…。
これらの要素を、シードルの「果実味」が優しく包み込み、「酸味」がチーズの脂を切り、「渋み(タンニン)」がそば粉の香ばしさと同調します。
これはもう、理屈抜きに「セットで生まれてきた」としか思えない完璧な組み合わせ。
私もカフェでガレットを頼む時は、迷わずシードル(できれば辛口)を選びます。このペアリングを知っているだけで、カフェランチの満足度が格段に上がりますよ。
Manamiのおすすめ!「いつもの食卓」が劇的に変わる万能ペアリング
ガレットだけがシードルの相棒ではありません。むしろ、私たちが普段食べている料理にこそ、シードルは寄り添ってくれます。
-
豚肉料理(ポークソテー、サムギョプサル、豚の角煮)
「リンゴと豚肉」は、料理の世界でも古くから鉄板の組み合わせ(アップルソースのポークソテーなど)。シードルの酸味が豚肉の脂を驚くほどさっぱりさせてくれます。特にサムギョプサル! ビールやマッコリも良いですが、辛口シードルを試してみてください。脂がすっきり流れて、無限に食べられそうになります(笑)。
また、豚の角煮のような「甘辛い」和食には、ほんのり甘みのある中辛口(ドゥミ・セック)が、醤油とみりんの風味に寄り添います。
-
中華料理(餃子、唐揚げ、春巻き)
これは私が最も推したい組み合わせの一つ。
餃子や唐揚げにビール、もちろん最高です。でも、シードルを合わせると、ビールの爽快感はそのままに、リンゴのフルーティーさが加わって、より「料理」としての一体感が生まれます。特に、酢醤油やラー油との相性が抜群なんです。
-
エスニック料理(タイカレー、生春巻き)
ワインを合わせるのが難しいエスニック。レモングラスの酸味、ココナッツミルクの甘み、唐辛子の辛さ…。
シードルの持つ「甘酸っぱさ」が、これらの要素と見事に調和します。ワインだと負けてしまうような強いスパイスも、シードルなら優しく受け止めてくれます。
-
チーズ(カマンベール、シェーブル)
シードルの産地であるノルマンディー地方は、カマンベールチーズの故郷でもあります。同じ土地で生まれたもの同士、合わないわけがありません。
カマンベールやブリーなど白カビタイプの、クリーミーでまろやかな味わいと、シードルの爽やかな酸味。最高です。
また、少しクセのあるシェーブル(ヤギのチーズ)の独特な酸味と、シードルの酸味がぶつからずに馴染みます。
初心者向け!シードルの選び方と感動するほど美味しくなる飲み方
「シードル、試してみたくなった! でも、どう選べばいい?」
「美味しく飲むためのコツは?」
最後に、シードルのポテンシャルを120%引き出す、実践的なアドバイスです。
最初の1本はどう選ぶ?
まずは、あなたの「シードル観」を覆すために、**フランス産(ノルマンディーかブルターニュ)の「ブリュット(辛口)」**から試してみることを強くおすすめします。
-
食事と合わせたい、複雑味を楽しみたい → フランス産の「辛口 (Brut)」
-
繊細でクリーンな味わいが好み、和食と合わせたい → 日本産(長野や青森)の「辛口」
-
デザートとして、またはお酒が弱い方 → フランス産の「甘口 (Doux)」
-
ビールのようにしっかりした飲みごたえが欲しい → イギリス産やアメリカ産の「Dry Cider」
【最重要】シードルは「ワイングラス」で飲みなさい!
これ、声を大にして言いたい、一番大切なポイントです。
シードルは、絶対に「ワイングラス」で飲んでください!
カフェなどで、コップや陶器のカップ(ブルターニュの伝統的なボウル)で出てくることがありますが、あれは雰囲気は良いものの、シードルの香りを閉じ込めてしまいます。
ビールジョッキやタンブラーなんてもってのほか。
シードルの命は、リンゴの華やかな香り、発酵や熟成による複雑な香りです。
いつもの白ワイングラスに、しっかり冷やしたシードルを注いでみてください。
グラスの中で繊細な泡が立ち上り、リンゴ、花、蜜、時にはナッツのような香りが一気に開きます。
「え、シードルってこんなに良い香りがしたの!?」
この体験をするだけで、シードルの印象は劇的に変わります。騙されたと思って、ぜひ。
美味しい温度と保存方法
-
温度:
白ワインやスパークリングワインと同じで、**しっかり冷やして(6℃〜10℃)**飲むのがベストです。ぬるいと、味わいがぼやけてしまいます。
-
保存方法:
発泡性なので、基本的には開栓したらその日のうちに飲み切るのが理想です。
もし飲みきれない場合は、シャンパンストッパー(スパークリングワイン用の密閉栓)を使ってしっかり栓をし、冷蔵庫で保存してください。1〜2日であれば、泡持ちも比較的良いです。
どこで買える?
数年前までは専門店でしか見かけませんでしたが、ブームのおかげで、今は驚くほど手に入りやすくなりました。
-
ワイン専門店(特にフランス産や日本産が豊富)
-
輸入食品店(カルディ、成城石井、紀ノ国屋など)
-
百貨店のお酒売り場
-
最近は、大きめのスーパーマーケットでも数種類は置いていることが多いです。
ぜひお酒売り場で、「ワイン」コーナーだけでなく、「ビール」や「RTD」コーナーの近くも探してみてくださいね。
まとめ:あなたの食卓に「リンゴの魔法」を
さて、ここまで「甘いジュースのお酒」というイメージを覆すべく、シードルの奥深い世界について、私の体験も交えながら熱く語ってまいりました。
もう一度、大切なポイントをおさらいしましょう。
-
シードルは、リンゴ100%から造られる**「リンゴの醸造酒」**。
-
甘口 (Doux) だけでなく、食事に最適な**「辛口 (Brut)」**がシードルの真骨頂。
-
専用品種(渋み!)を使うフランス産、高アルコールでドライなイギリス産、繊細な日本産など、産地によって個性豊か。
-
ガレットだけでなく、豚肉料理、中華、エスニック、チーズなど、実は「最強の食中酒」。
-
そして、**「ワイングラス」で「しっかり冷やして」**飲むこと。これが感動の第一歩です。
ビールではカジュアルすぎる、ワインでは重すぎる…。
そんな、ちょっと気分を上げたい平日の夜や、気取らない週末のランチに、シードルは完璧な答えをくれます。
「甘いお酒」という古いイメージは、今日でぜひ捨ててください。
次の週末は、お気に入りのワイングラスを準備して、「辛口シードル」を試してみませんか?
餃子や唐揚げ、ポークソテーと合わせれば、いつもの食卓が、きっと驚くほど華やかで、楽しいものになるはずです。
あなたの「推しシードル」と「最強ペアリング」が見つかったら、ぜひ私にも教えてくださいね!