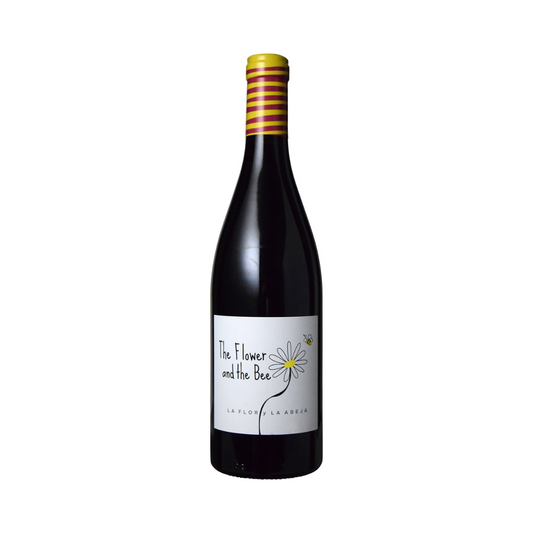こんにちは、CalivinoのManamiです。
先日、友人たちとホームパーティーを開いたときのこと。腕によりをかけて作ったローストビーフに合わせて、とっておきの赤ワインを開けました。「きっとこの濃厚な料理に合うはず!」と自信満々だったのですが、一口飲んだ友人から「わ、これ結構ガツンとくるね!」という一言が。
確かに、そのワインはアルコール度数が15%近くある、とてもパワフルな一本でした。美味しいけれど、お酒があまり強くない友人にとっては少し強すぎたようで、すぐに顔が赤くなってしまったんです。一方で、以前レストランで飲んだ白ワインは、アルコール度数が10%ほどですごく軽やか。「するすると飲めちゃうね!」なんて言いながら、ボトルがあっという間に空になったことも。
この経験から、「ワインのアルコール度数って、味わいや楽しみ方にこんなにも影響を与えるんだな」と改めて実感しました。
あなたも、こんな風に感じたことはありませんか?
-
「なんだか今日のワインは酔いが回りやすい気がする…」
-
「軽めに飲みたいけど、どのワインを選べばいいのかわからない」
-
「ラベルに書いてある『13.5%』という数字、これって高いの?低いの?」
ワインのラベルに小さく書かれているアルコール度数。普段はあまり気に留めないかもしれませんが、実はこの数字こそが、そのワインの個性や味わいを解き明かす重要な鍵なのです。
この記事では、ワインのアルコール度数に隠された秘密を、初心者の方にもわかりやすく、そして深く掘り下げてご紹介します。
-
なぜワインによってアルコール度数が違うの?その仕組みとは?
-
度数が味わいに与える驚くべき影響
-
もう迷わない!シーンや料理に合わせた度数別のワイン選び
-
健康的に楽しむための、賢いワインとの付き合い方
この記事を読み終える頃には、あなたはワインショップでラベルの数字を見るのが楽しくなっているはず。そして、ご自身の好みやその日の気分にぴったりの一本を、自信を持って選べるようになっているでしょう。ワインの世界がもっと広がり、毎日の食卓がさらに豊かになる。そんなヒントをたくさん詰め込みましたので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
ワインのアルコール度数、基本の「き」- 平均はどのくらい?
まず最初に、ワインのアルコール度数が一体どのくらいなのか、全体像を掴んでいきましょう。「ワインって、だいたいアルコール12%くらいでしょ?」と思っている方も多いかもしれませんが、実はその範囲は驚くほど広いんです。
日本の酒税法では、ワイン(果実酒)は「果実を原料として発酵させたもの」で、アルコール分が20度未満のもの(一部例外あり)と定義されています。つまり、法律上は最大で20%近くまでありえるということですね。
それでは、実際に私たちが普段楽しんでいるワインはどのくらいの度数なのでしょうか。種類別に平均的な数値を見てみましょう。
| ワインの種類 | 平均的なアルコール度数 | 特徴 |
| 赤ワイン | 12% 〜 15% | 一般的に白ワインよりも高め。力強く、飲みごたえのあるタイプが多い。 |
| 白ワイン | 10% 〜 13.5% | 赤ワインよりはやや低め。すっきりとした辛口から、甘口まで様々。 |
| ロゼワイン | 11% 〜 13% | 赤と白の中間くらい。製法によって味わいの幅が広い。 |
| スパークリングワイン | 11% 〜 12.5% | シャンパンやプロセッコなど。比較的標準的な度数。 |
| 酒精強化ワイン | 15% 〜 22% | ポートワインやシェリーなど。醸造過程でアルコールを添加するため非常に高い。 |
| 低アルコールワイン | 5.5% 〜 10% | ドイツの甘口ワインやイタリアの微発泡ワインなど。 |
いかがでしょうか?「低アルコール」と呼ばれる5.5%のものから、ポートワインのように20%を超えるものまで、実に様々ですよね。同じ赤ワインでも12%のものと15%のものでは、飲みごたえも酔い方も全く違ってきます。
ちなみに、ワインの歴史を遡ると、昔のワインは今よりもずっとアルコール度数が低かったと言われています。昔はブドウの栽培技術も未熟で、今ほど糖度の高いブドウを安定して作ることが難しかったためです。また、近年の地球温暖化の影響でブドウが完熟しやすくなり、世界的にワインのアルコール度数が上昇傾向にある、という専門家の指摘もあります。
まずはこの「ワインの度数には幅広いバリエーションがある」ということを知っておくだけで、ワイン選びの視点がぐっと広がりますよ。
なぜ?ワインによってアルコール度数が違う理由を徹底解説
では、どうしてこんなにもワインのアルコール度数に違いが生まれるのでしょうか。その秘密は、ワインの原料である「ブドウ」と、それがワインになるまでの「旅路」に隠されています。少し専門的な話も出てきますが、この仕組みがわかるとワインがもっと面白くなるので、ゆっくり解説していきますね。
1. ブドウの糖度が鍵!発酵のメカニズム
ワインのアルコールは、魔法のように生まれるわけではありません。その正体は、ブドウ果汁に含まれる糖分が、**酵母(こうぼ)**という小さな微生物の働きによって分解されて生まれるもの。このプロセスを「アルコール発酵」と呼びます。
簡単に言うと、こういうことです。
酵母がブドウの糖分を食べる → アルコールと二酸化炭素(スパークリングワインの泡の素)が生まれる
つまり、原料となるブドウの糖度が高ければ高いほど、酵母が食べられる糖がたくさんあるということ。その結果、生み出されるアルコールの量も多くなり、ワインのアルコール度数が高くなるのです。これが、アルコール度数を左右する最も基本的な大原則です。
「糖度が高いブドウ = アルコール度数が高くなるポテンシャルを秘めている」と覚えておいてください。
2. 産地の気候がブドウの糖度を決める
では、その重要な「ブドウの糖度」は何によって決まるのでしょうか。最も大きな要因が、ブドウが育った産地の気候です。
太陽の光をたっぷり浴びたブドウは、光合成を活発に行い、果実の中にたくさんの糖分を蓄えます。そのため、日照時間が長く、温暖な気候の産地ほど、糖度の高いブドウが育ちやすいのです。
-
温暖な産地(糖度が高くなりやすい → アルコール度数が高くなる傾向)
-
例: カリフォルニア(アメリカ)、南イタリア、スペイン南部、チリ、アルゼンチン、南オーストラリアなど
-
これらの産地のワインは、果実味が豊かでパワフル、アルコール度数も14%を超えるものが多く見られます。ラベルを見て「カリフォルニア産カベルネ・ソーヴィニヨン Alc. 14.5%」なんて書いてあったら、「ああ、太陽をたっぷり浴びて育ったんだな」と想像できますね。
-
-
冷涼な産地(糖度が上がりにくい → アルコール度数が低くなる傾向)
-
例: 北フランス(シャンパーニュ、ロワール)、ドイツ、オーストリア、北イタリアなど
-
これらの産地のワインは、繊細な酸味が特徴で、フレッシュで軽やかなスタイルになります。アルコール度数も12%前後、ドイツの甘口リースリングなどでは8%台のものも珍しくありません。
-
このように、ワインの産地を知ることは、そのワインのアルコール度数や味わいのスタイルを推測する大きなヒントになるのです。
3. ブドウの品種による違い
気候だけでなく、ブドウの品種そのものが持つ個性も、糖度の上がりやすさに影響します。人間にも日焼けしやすい人としにくい人がいるように、ブドウにも糖度を蓄えやすい「晩熟(ばんじゅく)タイプ」の品種と、そうでない「早熟(そうじゅく)タイプ」の品種があるんです。
-
糖度が上がりやすい品種(高アルコールになりやすい)
-
黒ブドウ: ジンファンデル、シラー(シラーズ)、グルナッシュ、マルベックなど
-
白ブドウ: シャルドネ(温暖な産地)、ヴィオニエ、ゲヴュルツトラミネールなど
-
-
糖度が上がりにくい品種(低アルコールになりやすい)
-
黒ブドウ: ガメイ、ピノ・ノワール(冷涼な産地)など
-
白ブドウ: リースリング、ソーヴィニヨン・ブラン(冷涼な産地)、ミュスカデなど
-
例えば、カリフォルニアのジンファンデルという品種は、非常に糖度が上がりやすいため、アルコール度数が15%を超えることもしばしば。一方で、ドイツのリースリングは冷涼な気候を好み、繊細な酸味を保つために糖度が上がりきる前に収穫されることが多く、アルコール度数は低めになります。
4. 収穫タイミングの重要性
同じ畑の同じ品種でも、いつ収穫するかによってブドウの糖度は大きく変わります。
-
早摘み: ブドウが完全に熟す前に収穫します。糖度は低く、酸味が高い状態なので、フレッシュで酸がキリっとした、アルコール度数の低いワインになります。
-
遅摘み(レイト・ハーヴェスト): 通常の収穫時期よりも長くブドウを樹にならせておきます。その間に水分が蒸発し、糖分が凝縮されるため、非常に糖度の高いブドウになります。デザートワインなど、極甘口でアルコール度数も高い(もしくは甘みを残すために発酵を途中で止める)ワインが造られます。
さらに特殊な例として「貴腐(きふ)ワイン」があります。これは特定の条件下でブドウに「貴腐菌」というカビが付着することで、果実の水分だけが蒸発し、糖分が極度に凝縮された状態のブドウから造られる甘口ワインです。世界三大貴腐ワインとして知られる「ソーテルヌ」などが有名ですね。
5. 醸造方法による調整
最後は、造り手である醸造家の腕の見せ所。ワインを造る過程でも、アルコール度数をある程度コントロールすることができるのです。
-
補糖(シャプタリザシオン): ブドウの糖度が足りず、目標とするアルコール度数に届かない場合に、発酵前に砂糖や濃縮ブドウ果汁を加える技術です。これは主に天候に恵まれなかった冷涼な産地で行われることがあります。ワインの甘さを加えるためではなく、あくまでアルコール度数を調整するために行われます。
-
発酵を途中で止める: 酵母が糖分をすべてアルコールに変えてしまう前に、冷却したり、硫黄(酸化防止剤)を添加したりして発酵をストップさせる方法です。こうすると、ワインの中に糖分が残るため甘口になり、アルコール度数は低く抑えられます。ドイツの甘口ワインや、イタリアの「モスカート・ダスティ」などがこの方法で造られます。
-
酒精強化(しゅせいきょうか): ワインの発酵途中、または発酵後にアルコール度数の高いブランデーなどの蒸留酒を添加する方法です。これにより、酵母の働きが止まり、糖分が残ったままアルコール度数が15%〜22%程度まで引き上げられます。スペインのシェリーやポルトガルのポートワインが代表的で、長期保存にも耐えうる力強いワインになります。
このように、ワインのアルコール度数は、ブドウが育った自然環境から、収穫のタイミング、そして醸造家の哲学や技術まで、様々な要因が複雑に絡み合って決まっているのです。一本のワインの裏には、壮大なストーリーがあるのですね。
【味わい編】アルコール度数がワインのキャラクターをどう変える?
さて、アルコール度数が決まる仕組みがわかったところで、次はその「度数」がワインの味わいに具体的にどんな影響を与えるのかを見ていきましょう。実は、アルコールは単に「酔うための成分」というだけではありません。ワインのボディ(飲みごたえ)や甘み、香りの感じ方まで、ワイン全体の印象を大きく左右する重要な要素なのです。
アルコール度数が高いワインの特徴:力強さと甘みの奥深さ
アルコール度数が14%を超えるようなワインを口に含んだ時、舌の上で「とろり」とした厚みや、喉を通る時の「カッ」とした熱っぽさを感じたことはありませんか?これが、アルコールがもたらすボディやボリューム感です。
-
豊かなボディと飲みごたえ: アルコールは液体に粘性を与える性質があります。そのため、度数が高いワインほど、口当たりがまろやかで、どっしりとした飲みごたえのある「フルボディ」に感じられます。逆に度数が低いワインは、水のようにサラッとした「ライトボディ」に感じられます。
-
ほのかな甘み: 実は、アルコールそのものにも甘みがあります。特に、発酵の副産物として生まれる「グリセロール」という成分は、ワインにまろやかさと甘みを与えてくれます。糖分が残っていない辛口の赤ワインでも、どこかふくよかな甘みを感じるのは、この高いアルコールとグリセロールのおかげなのです。
-
香りを引き立てる効果: アルコールは揮発性(気体になりやすい性質)が高いため、ワインに含まれる様々な香り成分を鼻まで運んでくれる役割も担っています。アルコール度数が高いワインは、グラスから立ち上る香りもより豊かで華やかに感じられる傾向があります。
<こんなワインが当てはまる!>
-
カリフォルニアのカベルネ・ソーヴィニヨンやジンファンデル
-
オーストラリア・バロッサヴァレーのシラーズ
-
南イタリアのプリミティーヴォ
-
スペイン・プリオラートのガルナッチャ
-
酒精強化ワイン(ポート、シェリーなど)
<ペアリングのヒント>
これらの力強いワインには、味わいの強さで負けない濃厚な料理がぴったり。牛肉のステーキやビーフシチュー、ラムチョップのグリル、ジビエ料理、熟成したハードタイプのチーズなどと合わせると、お互いの良さを引き立て合います。
アルコール度数が低いワインの特徴:繊細さとフレッシュな酸味
一方で、アルコール度数が12%以下のワインは、まったく異なる魅力を持っています。そのキーワードは「フレッシュ&デリケート」。
-
軽やかな飲み口: 度数が低いワインは、口当たりが非常に軽やかで、スイスイと飲めてしまいます。重たさがないので、飲み疲れしにくいのも特徴です。
-
際立つ酸味と果実味: アルコールのボリューム感が控えめな分、ブドウ本来が持つ**酸味(酸)**や、ピュアな果実の風味がストレートに感じられます。特に冷涼な産地で造られる白ワインは、レモンやグレープフルーツを思わせるような、シャープで心地よい酸味が魅力です。
-
繊細なアロマ: 香りも、パワフルで華やかなタイプというよりは、ハーブや白い花、柑橘類のような、繊細で清涼感のあるアロマが特徴的です。
<こんなワインが当てはまる!>
-
ドイツのリースリング(特にカビネットやシュペートレーゼ)
-
北イタリアのピノ・グリージョ
-
フランス・ロワール地方のミュスカデやソーヴィニヨン・ブラン
-
ポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデ
-
イタリアのモスカート・ダスティ
<ペアリングのヒント>
軽やかなスタイルのワインは、素材の味を活かした繊細な料理と相性抜群。魚介のカルパッチョやアクアパッツァ、白身魚のムニエル、フレッシュなサラダ、山羊のチーズなどと合わせてみてください。アペリティフ(食前酒)として、ワイン単体で楽しむのもおすすめです。
私の体験談:度数の違いで楽しむフードペアリング
以前、友人たちと「ワインの度数飲み比べ会」をしたことがあります。同じ「赤ワイン」というカテゴリーでも、全く違う楽しみ方ができることに皆で驚きました。
一つは、アルコール度数14.8%のオーストラリア産シラーズ。グラスに注ぐと、色が濃くて、脚(グラスの内側を伝うワインの雫)がとろりとしていました。香りはブラックベリーのジャムやチョコレート、スパイスのように濃厚。一口飲むと、凝縮された果実の甘みとアルコールの力強さが口いっぱいに広がります。これには、厚切りのビーフステーキを用意。ワインのパワフルさが、お肉の脂と旨味をしっかりと受け止めてくれて、まさに「至福」の組み合わせでした。
もう一つは、アルコール度数11.5%のフランス・ブルゴーニュ産ピノ・ノワール。こちらは対照的に、明るいルビー色で、グラスの中が透けて見えます。香りはラズベリーやチェリーのような赤い果実と、少し土やキノコのような繊細な香り。味わいはとてもエレガントで、なめらかな酸味が心地よく、余韻もきれい。このワインには、キノコのクリームパスタと鶏肉のハーブ焼きを合わせました。濃厚なシラーズとは違い、料理にそっと寄り添い、素材の風味を引き立ててくれるような、優しいペアリングを楽しめました。
このように、アルコール度数という指標を持つだけで、ワインの味わいを予測し、料理との相性を考えるのが格段に面白くなるんですよ。
【実践編】あなたに合う一本を見つける!度数別のワイン選びガイド
ワインのアルコール度数が持つ意味がわかってきたところで、いよいよ実践編です。知識を活かして、実際にあなたにぴったりの一本を選んでみましょう!お店でラベルを眺めながら、「さて、今日はどれにしようかな?」と考える時間が、きっと今まで以上に楽しくなりますよ。
シーン別おすすめアルコール度数
どんな時に、どんなワインを飲みたいか。シーンに合わせてアルコール度数を意識すると、ワイン選びの失敗がぐっと減ります。
-
乾杯やアペリティフ(食前酒)に【8%~12%】
これから始まる食事への期待を高める一杯には、軽やかで爽やかなタイプがおすすめです。アルコール度数が低めのスパークリングワインや、キリっと冷やした辛口の白ワイン(ソーヴィニヨン・ブランなど)が良いでしょう。胃に優しく、会話も弾みます。
-
平日のディナー、食事と一緒に楽しむなら【11%~13.5%】
毎日の食卓で、料理の味わいを引き立ててくれる名脇役。このあたりの度数のワインは、味わいのバランスが取れたものが多く、和食から洋食まで幅広い料理に合わせやすいのが魅力です。白ワインならシャルドネ、赤ワインならピノ・ノワールやメルローなどが定番です。
-
週末に、ワイン単体でじっくり味わうなら【14%以上】
読書をしたり、映画を観たりしながら、ゆっくりと時間をかけて楽しむ一杯。そんな時には、アルコール度数が高く、複雑で豊かな風味を持つワインがぴったりです。カリフォルニアのカベルネ・ソーヴィニヨンやイタリアのバローロなど、飲みごたえのあるフルボディの赤ワインを選んでみてはいかがでしょうか。チーズやナッツをお供にするのも素敵ですね。
-
お酒が弱い方や、軽めに楽しみたい休日のランチに【5.5%~10%】
「お酒は好きだけど、たくさんは飲めない…」という方や、翌日に影響を残したくない時には、低アルコールのワインが最適です。ドイツのリースリングやイタリアのモスカート・ダスティは、優しい甘みとフルーティーな香りで、アルコール度数が5.5%〜8%程度と非常に飲みやすいですよ。心地よい陽射しの中で楽しむランチにもぴったりです。
ラベルの読み方:アルコール度数表記はどこにある?
ワインのアルコール度数は、必ずラベルに記載することが法律で義務付けられています。どこに書かれているか、チェックしてみましょう。
-
表記の場所: 多くは、ボトルの正面に貼られているメインのラベル(エチケット)の下部に小さく書かれています。もし表ラベルになければ、裏の日本語表記ラベルを見てみてください。
-
表記の仕方: 「Alc. 13.5% by Vol.」や「13.5% vol.」のように記載されています。「Alc.」はAlcohol(アルコール)、「vol.」はVolume(容量)の略です。これは「容量に対するアルコールの割合」を示しています。
この数字を見るだけで、そのワインがどんなキャラクターなのか、大まかなスタイルを想像する手がかりになります。産地やブドウ品種の情報と組み合わせれば、もうあなたも立派なワイン通です!
賢いワインショップでの探し方・聞き方
もしお店で迷ってしまったら、遠慮なく店員さんに相談してみましょう。その際、「アルコール度数」をキーワードに質問すると、より具体的で的確なアドバイスがもらえますよ。
<質問の具体例>
-
「今日は魚料理に合わせたいので、アルコール度数が12%以下で、すっきりした白ワインはありますか?」
-
「しっかりとした飲みごたえのある赤ワインが好きです。アルコール度数が14%以上のもので、おすすめを教えてください。」
-
「お酒にあまり強くない友人と飲むのですが、度数が10%くらいまでで、少し甘口の飲みやすいワインを探しています。」
-
「このボルドーワインは**13%ですけど、こちらのカリフォルニアワインは14.5%**ですね。味わいはどう違いますか?」
このように具体的に質問することで、店員さんもあなたの好みを理解しやすくなり、理想の一本を提案してくれるはずです。ぜひ、勇気を出して話しかけてみてくださいね。
気になる健康との関係 - ワインの適量と賢い付き合い方
ワインは食事を豊かにし、心に潤いを与えてくれる素晴らしい飲み物ですが、やはりアルコール飲料。健康的に、そして長く楽しむためには、自分の「適量」を知り、賢く付き合うことがとても大切です。最後に、アルコール度数と健康について、少し考えてみましょう。
ワイン1杯の純アルコール量、計算できますか?
お酒の強さや健康への影響を考える上で重要になるのが、「純アルコール量」です。これは、飲んだお酒に含まれるアルコールの重さ(グラム)のことで、以下の計算式で求められます。
お酒の量(ml) × (アルコール度数(%) / 100) × 0.8(アルコールの比重) = 純アルコール量(g)
難しく感じるかもしれませんが、要は「量と度数を掛け合わせたものが大事」ということです。
例えば、アルコール度数の違うワインをグラス1杯(約120ml)飲んだ場合の純アルコール量を比較してみましょう。
-
A:アルコール度数10%の白ワイン
120ml × (10 / 100) × 0.8 = 9.6g
-
B:アルコール度数15%の赤ワイン
120ml × (15 / 100) × 0.8 = 14.4g
同じグラス1杯でも、アルコール度数が違うと、摂取するアルコールの量にはこれだけの差が出るのです。度数が高いワインを飲むときは、いつもよりペースを落としたり、量を控えめにしたりする意識が大切ですね。
ちなみに、ワインボトル1本(750ml)だとどうなるでしょうか。
-
アルコール度数12%のワイン1本 → 純アルコール量 約72g
-
アルコール度数14.5%のワイン1本 → 純アルコール量 約87g
こうして見ると、ボトル1本を一人で空けるのは、かなりのアルコール量になることがわかります。
厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」とは?
日本の厚生労働省は、健康リスクを低減するための飲酒量の指針として、「節度ある適度な飲酒は、1日平均純アルコールにして約20g程度」という量を示しています。
これを先ほどのワインに換算すると、
-
純アルコール量20g ≒ アルコール度数12%のワインで約208ml(グラス2杯弱)
ということになります。もちろん、これはあくまで平均的な目安であり、アルコールの分解能力には個人差(性別、年齢、体質など)が大きいため、自分にとっての適量を見つけることが何よりも重要です。
悪酔いを防ぐ、私のちょっとした工夫
ワインを美味しく、楽しく飲むために、私がいつも心がけていることがあります。当たり前のことばかりかもしれませんが、この一手間が翌日の快適さを大きく左右しますよ。
-
必ず「和らぎ水(やわらぎみず)」を用意する
これは日本酒の世界でよく言われる言葉ですが、ワインでも全く同じ。ワインを一口飲んだら、お水(チェイサー)も一口。血中アルコール濃度の上昇を緩やかにし、脱水症状を防いでくれます。何より、口の中がリフレッシュされて、次の一口がまた美味しく感じられます。
-
空腹で飲まない
空腹の状態でアルコールを摂取すると、胃を素通りして小腸で急速に吸収され、酔いが回りやすくなります。ワインを飲む前には、チーズやオリーブ、ナッツなど、少しでも何かお腹に入れておくようにしましょう。
-
ゆっくり、味わって飲む
特にアルコール度数が高いワインは、一気に飲むのではなく、香りや味わいの変化を楽しみながら、時間をかけてゆっくりと飲むのがおすすめです。そのワインが持つ複雑な魅力を堪能できますし、急激な酔いを防ぐことにも繋がります。
アルコール度数を意識することは、ワインをより深く味わうだけでなく、自分の体を守り、健康的にワインライフを続けるための大切なスキルなのです。
まとめ
今回は、「ワインのアルコール度数」という、少しマニアックだけれど、知れば知るほど面白いテーマを深掘りしてみました。
最後に、今日のポイントを振り返ってみましょう。
-
ワインのアルコール度数は**5.5%〜22%**と幅広く、種類や産地によって様々。
-
度数を決める最大の要因はブドウの糖度。そしてその糖度は、産地の気候やブドウ品種、収穫時期、醸造方法によって決まる。
-
アルコール度数は味わいに大きく影響し、高いと力強くリッチに、低いと繊細でフレッシュに感じられる。
-
ラベルの度数表記をチェックし、シーンや料理、自分の体調に合わせてワインを選ぶことで、楽しみ方は無限に広がる。
-
純アルコール量を意識し、和らぎ水と共にゆっくり楽しむことが、健康的なワインライフの秘訣。
今まで何気なく見ていたラベルの数字。その裏側には、太陽の恵みや大地の個性、そして造り手の情熱といった、壮大な物語が隠されています。アルコール度数は、その物語を読み解くための、いわば「ワインのプロフィール」のようなもの。
次にあなたがワインショップを訪れた際には、ぜひボトルの裏側までくるりと回して、アルコール度数にも注目してみてください。「このチリワインは14%か、太陽をたくさん浴びたんだな」「このドイツワインは8.5%だから、きっと優しい甘さなんだろうな」…そんな風に想像を膨らませるだけで、ワイン選びはもっと知的で、楽しい冒険になるはずです。
まずは、今日のディナーに合わせる一本から、アルコール度数を意識して選んでみませんか?きっと、あなたのワインの世界をさらに豊かに彩る、新しい発見が待っていますよ。
ぜひ、あなたのお気に入りの一本を見つけて、素敵なワインタイムをお過ごしくださいね!