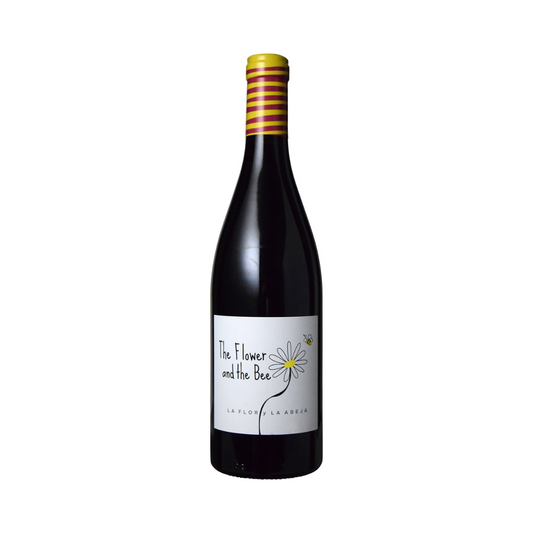こんにちは、CalivinoのManamiです。
ワインを片手に過ごす時間って、本当に素敵ですよね。レストランでのディナー、友人とのホームパーティー、あるいは一日の終わりに自分へのご褒美として楽しむ一杯。そのどれもが、日常を少しだけ特別なものに変えてくれます。
でも、そんな素敵なワインの時間で、ふと「あれ、私、ワイングラスの持ち方、これで合ってるのかな?」と不安になった経験はありませんか?
実は、何を隠そう、私自身がそうでした。ワインが好きで色々なお店に足を運ぶようになった20代の頃。周りの人たちがみんな、とてもエレガントにグラスを扱っているように見えて、「持ち方ひとつで、こんなにも印象って変わるんだ…」と、少しだけ気後れしてしまったことがあるんです。特に、初めて少し背伸びしたレストランに連れて行ってもらった時。目の前に置かれた薄くて繊細なグラスを前に、どこを持てばいいのか分からず、なんだかワインの味がしない…なんていう、ちょっぴり恥ずかしい思い出もあります。
「ボウル(膨らんだ部分)を持つと、手の温度でワインが温まっちゃうからダメよ」
「いやいや、国際的にはボウルを持つのが普通なんだって」
「指を揃えて、ステム(脚)を長く持つのが美しいのよ」
色々な情報が飛び交う中で、一体どれが本当なの?と混乱してしまいますよね。
でも、安心してください。ワイングラスの持ち方に「絶対的な正解」があるわけではありません。大切なのは、なぜその持ち方が推奨されるのかという理由を理解し、TPOに合わせてスマートに使い分けること。そして何より、自分自身がリラックスしてワインを楽しめることです。
この記事では、そんな私のちょっぴり恥ずかしい失敗談も交えながら、ワイングラスの持ち方の基本から、知っていると一目置かれる応用編、そして国際的なマナーの真実まで、徹底的に、そしてどこよりも分かりやすく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたはもうワイングラスの持ち方で迷うことはありません。どんなシーンでも自信を持って、堂々と、そしてエレガントにワインを楽しめるようになっているはずです。あなたのワインライフが、もっと豊かで素敵なものになるお手伝いができれば、こんなに嬉しいことはありません。
それでは一緒に、奥深いワイングラスの世界へ旅に出ましょう。
なぜ持ち方が重要?ワイングラスの各部位とその役割
まず、持ち方の話をする前に、私たちの手の中にある「ワイングラス」そのものについて、少しだけ理解を深めてみましょう。一見シンプルな形をしていますが、実は各部分にワインを最大限に楽しむための工夫が凝らされているんです。それぞれのパーツの名前と役割を知ることで、「なるほど、だからこの持ち方なんだ!」という納得感が格段にアップしますよ。
ワインの「顔」となる4つのパーツ
ワイングラスは、大きく分けて4つのパーツで構成されています。
-
リム(Rim): 唇が直接触れる、グラスの縁の部分です。このリムが薄ければ薄いほど、ワインが口の中にスムーズに流れ込み、味わいを繊細に感じ取ることができます。高級なグラスほど、このリムが驚くほど薄く仕上げられているんですよ。初めて良いグラスで飲んだ時、口当たりがなめらかで「いつものワインと違う!」と感じたのは、このリムのおかげだったのかもしれません。
-
ボウル(Bowl): ワインが注がれる、ふっくらと膨らんだ部分。ここがワインの香りを溜め込み、解き放つための最も重要な空間です。ワインの種類によって、このボウルの形が大きく異なるのをご存知でしたか?例えば、ボルドーワイン用のグラスは縦長で、豊かなタンニンを和らげ、香りをまっすぐ鼻に届けてくれます。一方、ブルゴーニュワイン用のグラスは、横に大きく膨らんだ風船のような形で、ピノ・ノワールのような華やかで複雑な香りをグラスの中に最大限に広げてくれるんです。このボウルの形状こそが、ワインのポテンシャルを最大限に引き出す鍵なのです。
-
ステム(Stem): ボウルを支える、細長い脚の部分。ここが、今回のテーマである「持ち方」の主役のひとつですね。ステムが存在する最大の理由は、手の温度をワインに伝えないため。ワインは非常にデリケートな飲み物で、温度が1〜2度変わるだけで、香りや味わいのバランスが大きく崩れてしまうことがあります。特に、キリッと冷やして楽しみたい白ワインやスパークリングワインにとって、体温は大敵。だからこそ、このステムを持って、ボウルに直接手が触れるのを避けるのが基本とされているのです。
-
プレート(Plate)/ フット(Foot): グラス全体を安定させる、底の円盤部分です。テーブルに置いた時の安定性を保つだけでなく、デザインの一部としても重要な役割を果たしています。このプレート部分を持って、プロのソムリエのようにテイスティングする方もいらっしゃいます。安定感は少し欠けますが、非常に優雅に見える持ち方です。
これらのパーツの名前と役割を頭の片隅に置いておくだけで、これからお話しする持ち方の理由が、スッと心に入ってくるはずです。グラスは単なる器ではなく、ワインの魅力を最大限に引き出すための「装置」なんですね。
【基本編】まずはこれをマスター!エレガントに見えるステムの持ち方
さて、ワイングラスの構造を理解したところで、いよいよ本題の「持ち方」です。まずは、日本国内のレストランやフォーマルな場で最も一般的で、かつ美しく見える「ステム(脚)を持つ」方法からマスターしましょう。これさえ押さえておけば、どんな場面でも恥ずかしい思いをすることはありません。
なぜステムを持つのが良いの?3つの明確な理由
なぜ多くの人がステムを持つことを推奨するのでしょうか。それには、見た目のエレガントさだけでなく、ワインを美味しく楽しむための、非常に合理的な理由があるのです。
-
ワインの温度を一定に保つため
先ほども少し触れましたが、これが最大の理由です。私たちの手のひらの温度は、だいたい34〜36度。一方、ワインの飲み頃温度は、スパークリングワインなら5〜8度、白ワインなら7〜14度、赤ワインでも15〜18度程度です。もしボウル部分を手のひらで包むように持ってしまうと、手の熱がダイレクトにワインに伝わり、あっという間に温度が上昇してしまいます。
特に繊細な白ワインやロゼワインは、温度が上がると香りがぼやけ、酸味のキレも失われ、ただ「ぬるいお酒」という印象になってしまうことも。せっかくソムリエがベストな温度で提供してくれたワインを、最後まで美味しくいただくための、一番の思いやりが「ステムを持つ」ことなのです。
-
ワインの色と「涙」を美しく鑑賞するため
ワインの楽しみは、味わいや香りだけではありません。その美しい「色」も大きな魅力のひとつ。ガーネット、ルビー、ゴールド、レモンイエロー…グラスに注がれたワインの色合いは、見ているだけでも心が豊かになりますよね。ボウルを持ってしまうと、指紋でグラスが曇ってしまい、この美しい色合いを純粋に楽しむことができません。
また、グラスを回した時に、内側を伝って落ちるワインの雫を「ワインの涙(または脚)」と呼びます。これはアルコールの度数や糖分の高さを示すもので、ワインの粘性を目で見て楽しむポイントのひとつ。ステムを持っていれば、この繊細な涙の様子もクリアに観察することができます。
-
所作が美しく、エレガントに見えるため
そして、やはり見た目の美しさは重要です。指先を揃えてスッとステムを持つ姿は、とても上品で洗練された印象を与えます。ボウルを鷲掴みにするのに比べて、所作に「余白」が生まれ、それが優雅さにつながるのです。特に、ドレスアップした素敵なレストランでは、このエレガントな所作が、その場の雰囲気をより一層引き立ててくれます。
実践!美しく見えるステムの持ち方3ステップ
では、具体的にどう持てば良いのでしょうか。ポイントは「力みすぎないこと」。リラックスして、指先で優しく支えるイメージです。
ステップ1:親指と人差し指でつまむ
まず、ステムの中ほどを、親指と人差し指の腹で、かるくつまむように持ちます。爪を立てたり、ぎゅっと力を入れたりする必要はありません。
ステップ2:中指をそっと添える
次に、人差し指の下に中指を添えます。この3本の指が、グラスを支えるメインの指になります。この3点で支えることで、グラスは驚くほど安定します。
ステップ3:薬指と小指は自然に流す
残りの薬指と小指は、力を抜いて、中指に沿わせるか、プレート(底)の上に軽く添えるようにします。無理に伸ばしたり、逆に固く握り込んだりすると不自然に見えてしまいます。あくまで自然に、リラックスさせておくのがポイントです。
どうでしょう?これだけで、なんだか手元がとても綺麗に見えませんか?
私が以前、ワインスクールの先生に教わったコツは、「鳥のヒナを優しく手で包むようなイメージ」で持つこと。力を入れすぎず、でも落とさないように、優しく、繊細に。このイメージを持つだけで、指先の所作が格段に美しくなりました。ぜひ試してみてください。
「スワリング」もスマートに!香りを引き出すグラスの回し方
ワインを飲む前、グラスをくるくると回す動作を見たことがあるかと思います。これを「スワリング」と言います。ワインを空気に触れさせることで、眠っていた香りを花開かせ、より豊かに楽しむためのテクニックです。このスワリングも、ステムを持っている方が断然やりやすいのです。
初心者のうちは、テーブルにグラスを置いたまま、プレートの縁を軽く押さえて、円を描くように回すのがおすすめです。慣れてきたら、グラスを持ち上げて、手首のスナップを効かせて回してみましょう。
ここでもちょっとしたコツが。回す方向は、**反時計回り(左回り)**がマナーとされています(左利きの方は時計回り)。なぜなら、もし万が一ワインがこぼれてしまった時に、自分の方にかかるだけで、向かいにいる相手に飛ばしてしまうのを防ぐため。これも、相手への配慮から生まれた美しいマナーですね。
ステムを持つ基本のスタイル。それはただの形式ではなく、ワインへの愛情と、周りの人への配慮が詰まった、とても合理的で美しい作法なのです。まずはこの持ち方を、ご自身のものにしてみてください。
【応用編】これってマナー違反?ボウルを持つのは本当にNGなのか
「ステムを持つのが基本なのは分かったけど、映画のワンシーンとかで、俳優さんが格好良くボウルを持って飲んでいるのを見たことがある…あれは間違いなの?」
「立食パーティーで、ステムを持っていたら不安定で、ワインをこぼしそうになったことがある…」
こんな風に思ったことはありませんか?実は、「ボウルを持つ」というスタイルにも、ちゃんとした理由と、それが許容される、あるいはむしろ推奨されるシーンが存在するのです。「ボウルを持つ=即マナー違反」と決めつけてしまうのは、少し早計かもしれません。
国際マナーの真実:「海外ではボウル持ちが主流」は本当?
よく「日本ではステムを持つのが主流だけど、海外、特にヨーロッパではボウルを持つのが一般的」という話を聞きます。これは、半分本当で、半分は誤解を含んでいます。
確かに、ヨーロッパのカジュアルなビストロやバル、家庭での食事風景などでは、ごく自然にボウル部分を持ってワインを楽しんでいる人々を多く見かけます。彼らにとってワインは日常の飲み物。安定感を重視し、リラックスしたスタイルで飲むのが当たり前なのです。
しかし、これが星付きの高級レストランや公式な晩餐会といったフォーマルな場になると話は別です。このような場では、国際的にもステムを持つのが正式なマナーとされています。テイスティングの際や、ワインの状態を確かめるときにソムリエがステムを持つように、やはりワインの温度変化を避け、色や香りを確認するという基本原則は世界共通なのです。
では、なぜ「海外ではボウル持ち」というイメージが広まったのでしょうか。一説には、昔のヨーロッパのグラスはステムが短く、装飾が施されているものが多く、ボウルを持たないと不安定だった時代の名残という説もあります。また、日常にワインが溶け込んでいる文化だからこそ、堅苦しいマナーよりも、その場を楽しむことを優先する、という考え方が根底にあるのかもしれませんね。
結論として、「海外ではボウル持ちが主流」というよりは、「カジュアルなシーンではボウル持ちも一般的」と理解するのが正確です。 ですから、海外のレストランで周りがボウルで持っていたとしても、あなたがステムで持っていてマナー違反になることは決してありません。むしろ、ワインを丁寧に扱っているという印象を与え、好意的に見られることの方が多いでしょう。
ボウルを持った方が良い、意外なシチュエーション
では、どのような時にボウルを持つのが理にかなっているのでしょうか。
-
立食パーティーや混雑した場所で
これが最も分かりやすい例です。グラスを片手に人と会話したり、移動したりする立食パーティー。細いステムだけを持っていると、誰かとぶつかった拍子にグラスが大きく揺れて、大切なワインをこぼしてしまう危険性があります。そんな時は、ボウルの下の方を指で支えるように持つと、格段に安定感が増します。周りの方のドレスを汚してしまったり、会場のカーペットにシミを作ってしまったりするリスクを考えれば、これは非常にスマートな選択と言えます。
-
赤ワインの香りを立たせたい時
これは少し上級者向けのテクニックですが、少し温度が低すぎる状態で提供されたフルボディの赤ワインなどの場合、あえてボウルを両手で包み込むようにして、手の温度で少しだけ温めてあげる、ということがあります。温度が少し上がることで、閉じていた香りが華やかに開き、タンニンもまろやかに感じられるようになるのです。ただし、これはあくまで意図的に行うもので、長時間温め続けるのは禁物。ワインの状態を見ながら、最適な瞬間を探る、まさにワインとの対話のような楽しみ方ですね。
-
ステムのないグラス(タンブラー)で飲む時
最近では、カジュアルでおしゃれなステムのないワイングラスも人気です。この場合は、当然ボウルを持つしかありません。その際は、なるべくグラスの下の方を持ち、ベタベタと指紋をつけないように配慮すると、より美しく見えます。
ボウルを持つ時の、美しい所作
ボウルを持つ場合でも、鷲掴みは避けたいところ。美しく見せるコツは、指を揃えて、ボウルの下半分を優しく包み込むように持つことです。親指、人差し指、中指でグラスを支え、薬指と小指は軽く添えるだけ。こうすることで、ボウル持ちでも品のある、こなれた印象を与えることができます。
大切なのは、「なぜその持ち方を選ぶのか」という意識を持つこと。安定性を優先するのか、温度管理を優先するのか。その場の状況を判断し、最もふさわしい持ち方を自分で選択できることこそ、真のワイン愛好家と言えるのかもしれませんね。
【TPO別】シーンに合わせた完璧なグラスの持ち方ガイド
これまで、ステム持ちとボウル持ち、それぞれのメリットと背景について解説してきました。ここからは、より具体的に、私たちがワインを飲む様々なシーンを想定して、「こんな時は、こう持つのがベスト!」という実践的なガイドをお届けします。これを読めば、もうどんなシチュエATIONでも迷うことはありません。
ケース1:格式高いレストランでのディナー
結論:迷わず「ステム持ち」でエレガントに
記念日や特別な接待など、フォーマルなレストランでの食事。ここでは、間違いなく基本のステム持ちが最もふさわしい選択です。
-
理由:
-
場の雰囲気に合わせる:洗練された空間、美しいカトラリー、そしてプロフェッショナルなサービス。そのすべてに敬意を払い、自分自身の所作もエレガントに保つのが大人のマナーです。
-
ソムリエへの敬意:ソムリエは、そのワインが最も輝くであろう完璧な温度でサービスしてくれています。その努力を無にしないためにも、手の温度が伝わらないステム持ちを徹底しましょう。
-
テイスティングの機会:もしあなたがホスト役でテイスティング(ワインの状態を確認する試飲)を任された場合、ステムを持って色を確認し、スワリングで香りを確かめるという一連の動作が非常にスムーズに行えます。
-
-
Manami's Point:
私も、初めて訪れる高級フレンチでは、少し緊張しながらも背筋を伸ばし、指先まで意識してステムを持つようにしています。その緊張感も含めて、非日常の特別な体験の一部だと楽しむようにしています。グラスの扱い方が美しいと、サービスする側からも「ワインをご存知の方だな」と一目置かれ、より丁寧なサービスを受けられる…なんてこともあるかもしれませんよ。
ケース2:友人たちとの賑やかなホームパーティー
結論:「ステム持ち」を基本としつつ、状況に応じて「ボウル持ち」もOK!
気心の知れた友人たちと、リラックスして楽しむホームパーティー。ここでは、あまり堅苦しく考えすぎる必要はありません。
-
理由:
-
基本はステム持ちで:座ってゆっくり話しながら飲む時は、やはりステム持ちがおすすめです。ワインの温度を保てますし、習慣づけておくと自然で美しい所作が身につきます。
-
立ったり座ったり、移動が多い時は:キッチンに料理を取りに行ったり、別のグループの会話に加わったり。動きが多い場面では、前述の通り、安定感を重視してボウルを下から支えるように持つのが賢明です。ワインをこぼしてしまうことの方が、よっぽどマナー違反ですから。
-
-
Manami's Point:
私の家のワインパーティーでは、あえてステムのないカジュアルなグラスをいくつか用意しておくこともあります。そうすると、ゲストも「今日は気軽に楽しんでいいんだな」とリラックスしてくれます。大切なのは、ルールに縛られることよりも、その場の誰もが心地よく過ごせる雰囲気を作ることですよね。
ケース3:ワインの試飲会(テイスティングイベント)
結論:プロに倣い、機能性を重視した「ステム持ち」を
多くの種類のワインを少量ずつ試飲するテイスティングイベント。ここでは、楽しむだけでなく「分析する」という目的も加わります。
-
理由:
-
正確な評価のために:ワインの色、香り、味わいを正確に評価するためには、温度変化は厳禁です。プロのソムリエや醸造家が必ずステムを持つように、私たちもそのスタイルに倣いましょう。
-
スワリングの重要性:次々と新しいワインを試す中で、スワリングで香りを引き出す作業は欠かせません。ステムを持っていれば、この動作が容易に行えます。
-
メモを取りながら:多くの試飲会では、メモを取ることが推奨されます。グラスを置かずに片手でテイスティングノートを書き込む際も、ステムを指の間に挟むように持つと安定します。
-
-
Manami's Point:
試飲会では、首から下げるタイプのグラスホルダーがとても便利ですよ!両手が自由になるので、メモを取ったり、おつまみを取ったりするのに重宝します。そして、たくさんのワインを試すうちに、どのグラスが自分のだったか分からなくならないように、グラスのプレート部分に貼れるチャームやマーカーを持っていくのも、ちょっとした上級者テクニックです。
ケース4:屋外でのピクニックやバーベキュー
結論:割れないグラスで、安定感抜群の「ボウル持ち」を!
青空の下で楽しむワインは格別ですよね。しかし、屋外ではテーブルが不安定だったり、風が強かったりすることも。
-
理由:
-
安全性と安定性:屋外では、倒れにくいプラスチック製やトライタン製のステムがない、あるいはステムが短いグラスがおすすめです。その場合は必然的にボウルを持つことになりますが、それが最も安全で理にかなっています。
-
温度はクーラーボックスで:屋外では、そもそもグラスを持つ手からの温度以上に、外気温の影響を大きく受けます。ワインの温度を保つには、持ち方よりも、ワインボトルをしっかりとクーラーボックスやアイスバケツで冷やし続けることの方が重要です。
-
-
Manami's Point:
最近のアウトドア用ワイングッズは本当におしゃれで機能的!保冷機能のあるタンブラーや、地面に突き刺して使えるグラスホルダーなど、便利なアイテムがたくさんあります。こういったグッズを活用して、屋外でもスマートにワインを楽しみたいですね。
このように、絶対的な正解を求めるのではなく、その場の状況や目的に合わせて、最適な持ち方を柔軟に選択できるのが、真にワインを楽しんでいる人の姿ではないでしょうか。
【まとめ】もう迷わない!自信が持てるワイングラスの持ち方
さて、ワイングラスの持ち方を巡る長い旅も、そろそろ終わりに近づいてきました。ここまで読んでくださったあなたは、もうワイングラスを前にして、持ち方で戸惑うことはないはずです。
最後に、今日の内容をぎゅっと凝縮して、大切なポイントを振り返ってみましょう。
1. ワイングラスの基本は「ステム(脚)持ち」
-
理由: 手の温度でワインが温まるのを防ぎ、最後まで美味しく飲むため。ワインの美しい色や「涙」を楽しむため。そして何より、所作がエレガントに見えるため。
-
持ち方のコツ: 親指・人差し指・中指の3本で優しく支え、力まないこと。
2. 「ボウル(膨らんだ部分)持ち」もTPOによってはOK!
-
「海外ではボウル持ちが主流」は誤解も: フォーマルな場では世界共通でステム持ちがマナー。カジュアルなシーンで安定感を求めて持つのが一般的です。
-
ボウル持ちが推奨される場面: 立食パーティーなど、グラスが不安定になりがちな混雑した場所。
3. シーンに合わせて持ち方を使い分けるのが真の上級者
-
フォーマルなレストラン: 迷わず「ステム持ち」で、場の雰囲気に合わせたエレガントな所作を。
-
カジュアルなパーティー: 「ステム持ち」を基本に、移動時は安定する「ボウル持ち」も活用。
-
テイスティング: ワインを正しく評価するために、機能性を重視した「ステム持ち」を徹底。
-
アウトドア: 安全第一!割れないグラスで安定感のある持ち方を。
4. 最も大切なのは「リラックスして楽しむ心」
マナーや形式も大切ですが、それに縛られすぎてワインの味がしなくなってしまっては本末転倒です。なぜそのマナーがあるのかという背景を理解した上で、最終的にはあなたが一番心地よいと感じる方法で、目の前の一杯を心から楽しむこと。それが何よりの「正解」だと私は思います。
かつて、持ち方が分からずにドキドキしていた私も、今ではどんなシーンでも自信を持ってグラスを手に取れるようになりました。それは、たくさんの失敗や経験を通じて、「自分なりのワインとの付き合い方」を見つけられたからかもしれません。
このブログが、あなたのそんな「自分らしいスタイル」を見つけるための一助となれたなら、これほど嬉しいことはありません。
さあ、今夜はいつもより少しだけ指先を意識して、ワイングラスを手に取ってみませんか?きっと、いつものワインが、もっともっと美味しく、愛おしく感じられるはずです。
ぜひ、次のワイン会やレストランでのディナーで、今日学んだことを実践してみてくださいね。あなたのワインライフが、より一層輝きに満ちたものになりますように。