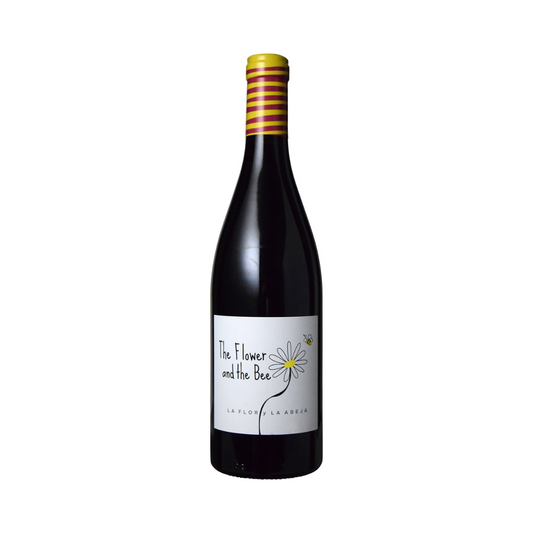こんにちは、CalivinoのManamiです。
よく晴れた週末の昼下がり、テラス席が心地よいカフェでのランチ。目の前には彩り豊かなサラダと焼きたてのパン。こんな時、「あぁ、グラス一杯のキリッとした白ワインがあれば、最高なのに…」なんて思うこと、ありませんか?
でも、その後に予定があったり、車の運転があったり、あるいはお酒にそれほど強くなくて、昼間から飲むとすぐに眠くなってしまう…。そんな風に考えて、せっかくのワインを諦めてしまうこと、私にもよくありました。ワインは大好きだけれど、いつでも気兼ねなく楽しめるわけじゃない。そのジレンマが、ずっと心のどこかにあったんです。
しかし最近、そんな私の悩みをすっきりと解決してくれる、素晴らしい選択肢が登場し、世界的なトレンドになっています。それが、今回ご紹介する**「低アルコールワイン」**です。
「低アルコール」と聞くと、「味が薄いんじゃないの?」「ジュースみたいで物足りなさそう…」なんて、少しネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。でも、それは大きな誤解です。現在の低アルコールワインは、製造技術の目覚ましい進化によって、ブドウ本来の豊かな風味や香りを保ちながら、アルコール度数だけを抑えた、非常にクオリティの高いものが増えています。
この記事は、
-
お酒には強くないけれど、ワインの雰囲気を楽しみたい
-
健康やカロリーを意識しながら、ワインを飲みたい
-
昼間の食事やオンライン飲み会などで、気軽にワインを楽しみたい
-
ワインが好きだからこそ、飲むシーンを我慢したくない
そんな、すべてのワイン好きのあなたのための、新しい扉を開くガイドブックです。この記事を読み終える頃には、あなたは低アルコールワインの魅力とその選び方をマスターし、これまで以上に自由で豊かなワインライフを送れるようになっているはず。
さあ、我慢から解放される、軽やかで美味しいワインの世界を一緒に覗いてみましょう!
そもそも「低アルコールワイン」って何?ノンアルとの違いは?
まず最初に、言葉の定義をはっきりさせておきましょう。「低アルコールワイン」とは、その名の通り、通常のワインよりもアルコール度数が低く造られたワインのことです。
日本の法律で明確な定義があるわけではありませんが、一般的にワインのアルコール度数は12%〜14%程度のものが多いのに対し、**5%〜10%前後のものが「低アルコールワイン」**と呼ばれています。ビールと同じくらいの度数か、それよりも少し高いくらい、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
ここで非常に大切なのが、「ノンアルコールワイン」との違いです。この二つは、似ているようで全くの別物なのです。
| 種類 | アルコール度数 | 特徴 |
| 低アルコールワイン | 約5%〜10% | 通常のワインと同様に醸造された「ワイン」。ブドウの風味豊か。 |
| ノンアルコールワイン | 1%未満 | 一度ワインを造ってからアルコールを除去したもの。酒税法上は「清涼飲料水」。 |
| ワインテイスト飲料 | 0.00% | ブドウ果汁に香料などを加え、ワインの味に似せた「ジュース」。 |
ポイントは、低アルコールワインは、あくまで「ワイン(お酒)」であるということ。ブドウを発酵させて造るという、ワインの最も重要な工程を経て生まれます。そのため、ノンアルコールワインやワインテイスト飲料では再現しきれない、ブドウ本来の複雑な香りや、発酵由来の奥深い味わいをしっかりと楽しむことができるのです。
近年、世界的に健康志向が高まり、「Sober Curious(ソバーキュリアス)」という、「お酒は飲めるけれど、あえて飲まない、もしくは少量しか楽しまない」というライフスタイルが注目されています。そんな時代の流れの中で、「罪悪感なく、美味しく楽しめる」低アルコールワインは、まさに現代人のニーズにマッチした、新しい選択肢として人気を集めているのです。
どうやって造られるの?アルコール度数を抑える3つの秘密
「ブドウの風味はそのままに、アルコールだけを低くするなんて、どうやって?」と不思議に思いますよね。低アルコールワインを造るアプローチは、主に3つあります。その製造方法を知ると、ワイン選びがさらに面白くなりますよ。
秘密1:ブドウの糖度が上がる前に「早摘み」する
ワインのアルコールは、ブドウ果汁に含まれる「糖分」を、酵母が分解することで生まれます。つまり、原料となるブドウの糖度が低ければ、結果的に生成されるアルコールも低くなる、というわけです。
そこで用いられるのが、ブドウが完熟して糖度が上がりきる前の、少し早い段階で収穫する「早摘み」という手法です。
-
メリット:フレッシュで酸味がキリッとした、爽やかな味わいのワインになります。
-
デメリット:完熟果実のような豊かな甘みや複雑味は出にくく、少し青々しい(グリーンの)ニュアンスが出ることがあります。
この手法は、軽やかなスタイルの白ワインやロゼワインでよく見られます。
秘密2:気候が涼しい「冷涼な産地」で自然に造る
そもそも、ブドウの糖度は日照量に大きく影響されます。さんさんと太陽が降り注ぐ温暖な地域ではブドウはよく熟し糖度が高くなりますが、逆にドイツやフランス北部のような「冷涼な産地」では、日照量が限られるため、ブドウの糖度が上がりにくくなります。
その結果、ワインは自然とアルコール度数が低めに仕上がる傾向があります。これは、人為的な操作ではなく、その土地のテロワール(ブドウが育つ環境)が生み出した、伝統的なスタイルです。
-
代表的なワイン:ドイツのリースリング(特に「カビネット」という等級)、ポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデなど。
-
特徴:豊かな酸味と繊細な果実味、そして美しいミネラル感が特徴で、非常にエレガントな味わいです。
秘密3:最先端の「脱アルコール技術」を駆使する
最も革新的なのが、一度通常のワインを造った後で、最先端の技術を用いてアルコール分だけを取り除く、という方法です。これにより、ワインが本来持っている豊かな香りや味わいを損なうことなく、アルコール度数だけを自由にコントロールすることが可能になりました。
-
逆浸透膜(RO)法:非常に目の細かい特殊なフィルターを使い、ワインからアルコールと水だけを分離させ、その後、水を戻す方法。アロマ成分を失いにくいのが特徴です。
-
スピニング・コーン・コラム法:遠心力を利用してワインを薄い膜状に広げ、低温・真空状態で穏やかにアルコール分を気化させる方法。熱によるダメージが少ないため、ワインの繊細な香りを保つのに優れています。
これらの技術のおかげで、以前の「気の抜けたジュースのよう」というイメージは完全に覆され、本格的な味わいの低アルコールワインが次々と生まれています。
あなたにぴったりの一本を見つける!低アルコールワインの選び方
さて、低アルコールワインの魅力と背景が分かったところで、いよいよ実践編です。数あるワインの中から、どうやってお気に入りの一本を見つければ良いのでしょうか?3つの簡単なステップでご紹介します。
ステップ1:まずはラベルの「アルコール分」をチェック!
最も確実で簡単な方法です。ワインボトルの裏ラベルには、必ず「アルコール分」や「alc.」といった表記で、アルコール度数がパーセンテージで記載されています。
まずは、この数字を見る習慣をつけましょう。「10%以下」が一つの目安になります。お気に入りのワインを見つけたら、その度数を覚えておき、次のお店で「アルコール10%以下のワインはありますか?」と聞いてみるのも良い方法です。
ステップ2:特定の「産地」や「ブドウ品種」を狙う
前述の「冷涼な産地」で造られるワインは、低アルコールの宝庫です。ワインショップで、以下のキーワードを探してみてください。
【白ワインのおすすめ】
-
モスカート・ダスティ(イタリア):アルコール度数は5.5%前後。マスカットの華やかな香りと、優しい甘さ、そして微発泡が特徴。ワイン初心者の方にも大人気の、間違いのない一本です。
-
リースリング(ドイツ):特に「カビネット」や「シュペートレーゼ」といった等級のものは、アルコールが7%〜9%程度と低めで、繊細な甘みと美しい酸味のバランスが絶妙です。
-
ヴィーニョ・ヴェルデ(ポルトガル):「緑のワイン」を意味する、フレッシュで爽やかな微発泡性の白ワイン。アルコールは9%〜11%程度で、シーフードとの相性は抜群です。
【赤ワインのおすすめ】
一般的に、赤ワインは白ワインよりもアルコール度数が高くなる傾向があり、低アルコールの選択肢は少なめです。しかし、中には軽やかなスタイルのものも存在します。
-
ドルンフェルダー(ドイツ):ドイツで人気の赤ワイン用ブドウ。穏やかなタンニンと、ベリー系のチャーミングな果実味が特徴で、アルコール度数も比較的低めのものが多く見られます。
-
ブラケット・ダックイ(イタリア):赤いバラのような華やかな香りと、イチゴを思わせる甘酸っぱい味わいが魅力の、甘口の赤の微発泡ワイン。アルコールは5%〜6%程度です。
ステップ3:「甘口」か「辛口」か、好みの味わいで選ぶ
低アルコールワインを選ぶ上で、味わいの「甘辛度」は重要なポイントです。
-
甘口(あまくち)を選びたい方
アルコール発酵を途中で止めて造るタイプのワインは、ブドウの糖分がワインの中に残るため、自然と甘口になります。モスカート・ダスティやドイツのリースリング、ブラケット・ダックイなどは、その代表格です。優しい甘さは、疲れた心と体を癒してくれます。
-
辛口(からくち)を選びたい方
食事に合わせやすい、スッキリとした辛口が好みの方は、ヴィーニョ・ヴェルデがまずおすすめです。また、最近では脱アルコール技術を用いて造られた、本格的な辛口の低アルコールワインも増えています。「低アルコール 辛口」といったキーワードで探してみると、新たな発見があるかもしれません。
軽やかさは正義!低アルコールワインがもたらす嬉しいメリット
最後に、低アルコールワインを選ぶことが、私たちのワインライフにどんな素敵な変化をもたらしてくれるのか、そのメリットを整理してみましょう。
-
体への負担が少ない(ヘルシー!)
アルコール度数が低い分、肝臓への負担が軽減されます。また、一般的にアルコール度数とカロリーは比例する傾向にあるため、低カロリーなのも嬉しいポイント。飲みすぎによる二日酔いのリスクも低減できます。
-
飲むシーンが格段に広がる
これまで諦めていた、平日のランチやピクニック、読書のお供など、あらゆるシーンで気軽にワインを楽しめるようになります。「この後、もうひと頑張りしたい」という時でも、低アルコールワインならスマートな選択肢になります。
-
料理の繊細な味わいを引き立てる
アルコールのボリューム感が強いワインは、時として料理の繊細な風味を覆い隠してしまうことがあります。その点、軽やかな低アルコールワインは、素材の味にそっと寄り添い、その魅力を引き立てる名脇役になってくれます。特に、和食やエスニック料理など、これまでワインと合わせるのが少し難しいと感じていた料理とも、素晴らしい相性を見せてくれます。
まとめ:我慢しない、新しいワインの楽しみ方へ
いかがでしたか?低アルコールワインは、決して「通常のワインの代替品」や「妥協の選択肢」ではありません。それは、私たちのライフスタイルをより豊かに、そしてワインとの付き合い方をより自由にしてくれる、積極的でポジティブな新しい選択なのです。
-
低アルコールワインは、アルコール5%〜10%程度の本格的な「ワイン」
-
造り方は「早摘み」「冷涼な産地」「脱アルコール技術」の3つ
-
選ぶ時は「ラベル」「産地や品種」「甘辛度」をチェック
-
モスカート・ダスティ、ドイツのリースリング、ヴィーニョ・ヴェルデが狙い目
「ワインは好きだけど、飲むと色々気になってしまう…」
もしあなたがそう感じているのなら、ぜひ一度、低アルコールワインを手に取ってみてください。その軽やかで優しい味わいは、きっとあなたのワインの世界を、もっと広くて心地よい場所へと変えてくれるはずです。
次の週末は、ランチのお供にキリッと冷やしたヴィーニョ・ヴェルデはいかがですか?あるいは、一週間のご褒美に、華やかな香りのモスカート・ダスティで乾杯するのも素敵ですね。
我慢しない、新しいワインの扉を開けて、あなたらしい楽しみ方を見つけてみてください。